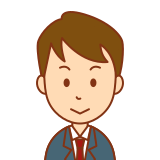
雨の日が続くと洗濯物が乾かない!
なんかいい方法ないの?
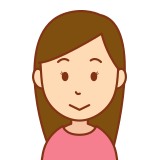
我が家は洗濯物のジャングルと化しています!
助けてください!
こんな状態になっている方も多いのではないでしょうか。
「ああ、洗濯物が増える!そして乾かない!!」

洗濯物を早く乾かすには、いかに水分を早く取り除くか(乾燥させるか)が勝負
もちろん、エアコンを除湿にしたりコインランドリーに持ち込んだりする方法もありますが、それではお金や時間もかかります。
この記事では、できるだけ低コストで洗濯物を少しでも早く乾かす方法をご紹介します。
洗濯物を早く乾かすコツ① 脱水の前に乾いたタオルを洗濯機に入れる
1つ目は、「脱水の前に乾いたタオルを洗濯槽の中に入れる」です。
洗ってすすいだ後には、脱水が始まります。その脱水が始まる前に洗濯機を止めて、乾いたタオルを入れます。

それから脱水すると乾いたタオルが水分を吸うので、ほかの洗濯物の水分が少なくなって乾きやすくなります。(その分、タオルも洗濯物になってしまいますが・・・)。
ただし、黒いズボンなどホコリが目立ちやすい服がある場合には、洗濯ネットに入れて洗うなど注意が必要です。
洗濯物を早く乾かすコツ② 干す位置を工夫する
次は、洗濯をした後の工夫です。
洗濯物を乾かすには、洗濯物の周りの湿度はできるだけ低い方がいいです。

部屋の湿度は、低いところに集まる性質があります。
そのため洗濯物を部屋干しするときは、天井近くの高いところに干したほうが早く乾きます。
壁際に干すと空気の流れが起こりにくいので、部屋の真ん中に干すことも大切です。
洗濯物を早く乾かすコツ③ 洗濯物の上下に新聞紙を置く
3つ目のコツは、「洗濯物の上下に新聞紙を置く」です。
新聞紙には除湿の効果があるらしく、洗濯物の上下に新聞紙を置くと、除湿器の役割を果たしてくれます。

洗濯物を干した部屋の床には、古新聞を敷き詰めましょう。
湿度が溜まりやすい下だけでもいいのですが、ピンチハンガーで吊るすときは上にも新聞紙を挟み込むと除湿効果が増します。
新聞紙をクシャクシャにして置くと表面の面積が大きくなるので、より除湿効果が期待できます。
洗濯物を早く乾かすコツ④ 洗濯物を裏返して干す
布の厚い服などは、裏返して干しましょう。
縫い目やポケットなどに風が当たり、早く乾かすことができます。
裏返しておくと洗うときは表面の生地が擦れないので傷みにくく、外に干すときも日に当たるのが裏側なので色あせ防止になります。
洗濯前に一つひとつ裏返すのは手間なので、脱いだときに裏返したまま洗濯機に入れておくといいでしょう。
洗濯物を早く乾かすコツ⑤ アーチ干しが理想的
アーチ干しも効果的です。
アーチ干しというのは長いものを両端に、短いものを真ん中に吊るす干し方です。
こうすると洗濯物を横から見たとき、アーチのように真ん中がくぼんで見えます。
アーチ干しにすると洗濯物の中で上昇気流が発生し、空気が動いて洗濯物が早く乾きます。
なにより簡単なのは「風を当てること」
洗濯物には水分が含まれています。いかに水分を取り除くが大切・・・。
と、いうことは、いちばん簡単なのは、風を当てることです。
吊るした洗濯物は下部が乾きにくいので、下半分に向けて扇風機やサーキュレーターの風を当てましょう。首振り機能を使うと、さらに効果的です。

是非、洗濯物の主である子供たちにうちわであおいでもらいましょう!
まとめ
この記事では、低コストで洗濯物を早く乾かすコツをご紹介しました。
洗濯物を早く乾かすには、いかに水分を早く取り除くか(乾燥させるか)がポイントになります。
雨の日が続いたりすると洗濯物はあふれ出ますが、この記事でご紹介した内容を試していただければ、少し早く洗濯物を乾かすことができます。
そして、この記事を読んでいただいた方のストレスも少し解消されますように。

おまけ
このたび、我が家では、子供へのお金の教育について実践した模様を電子書籍(kindle版)にして出版しました!その書籍がこちらです!
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XVHJ5P7/ref=cm_sw_r_tw_dp_7RMX4CK1SNP1KRGC1ZFP
我が家で行った家庭内起業の模様をまとめたものです。
お子さんのマネーリテラシーを向上させたい方は必見です。
また、実は、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、ポチっとお願いします。すっごく励みになります♪
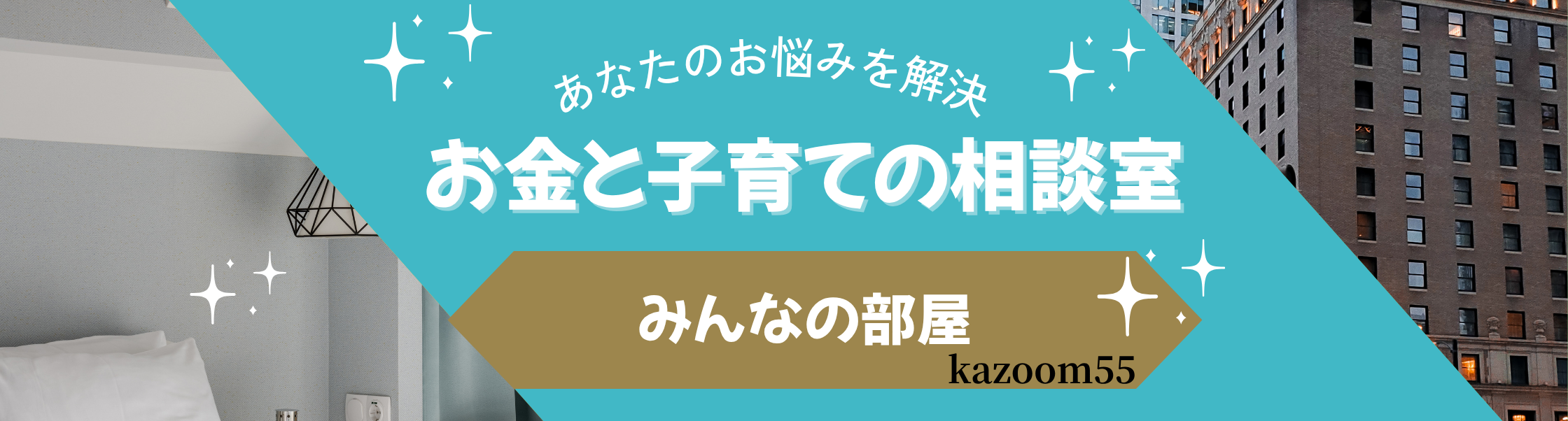




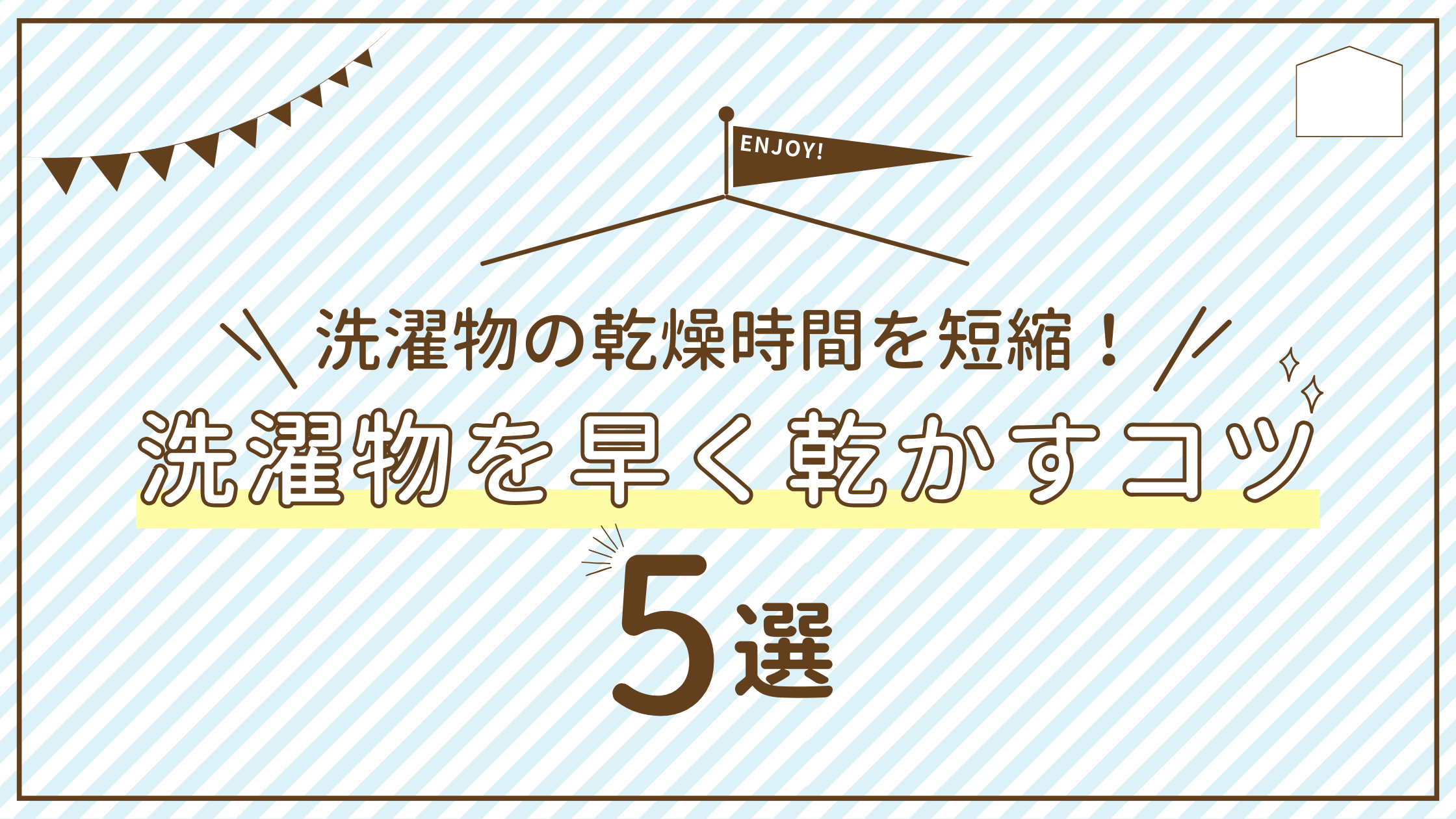


コメント
どれも効果的ですね!
参考になりました😄
ありがとうございます
洗濯ものとの闘いの参考になれば嬉しいです(^^♪