こどもにお金の話、どう切り出せばいいか分からない
「金融教育が大事なのは分かっている」
でも実際は、
・お金の話をすると嫌がられそう
・難しい説明になりそう
・そもそも親が自信を持って語れない
そんな理由で、何もできないまま時間だけが過ぎていく家庭がほとんどではないでしょうか。
我が家も、まさにそうでした。
そこで思い切って選んだのが、「お年玉を使った『体験型の金融教育』」です。
我が家ではお年玉を使った投資を実践した結果、子どもたちに「働いて稼ぐ」以外の選択肢を示すことができました。
そこで、この記事では、我が家での実践例を基に、簡単に始めることができる体験型の金融教育をご紹介します。
この記事を読んでいただくことで、各ご家庭の金融リテラシーが向上するきっかけを作ることができます。
なぜ「お年玉×投資」が金融教育に向いているのか
お年玉は、金融教育において極めて優秀な教材です。
理由はシンプルです。
・子ども自身が「自分のお金」と強く認識している
・一度にまとまった金額が入る
・正月という非日常で、話を聞いてもらいやすい
つまり、お金の話が最も素直に届くタイミングです。
よく「お年玉=貯金」というご家庭が多いですが、このチャンスを「貯金して終わり」にするのは、正直もったいないです。
最初に教えたのは「増やし方」ではなく3つの前提
投資を「儲け話」と誤解させないため、最初に伝えたのは次の3点だけです。
・お金は「使う・貯める」以外に「働かせる」ことができる
・増えることもあれば、減ることもある
・結果は親ではなく、自分が引き受ける
この前提を共有しただけで、子どもたちの向き合い方が明らかに変わりました。
年齢別に見えた「金融リテラシーの育ち方」
ここでは具体的に我が家の子どもたちが、どんなものに投資をして何を学んだのかをご紹介します。
長男(高校生)|数字と社会を結びつけて考える力
長男が選んだのは、日本個別株!
これを選んだ長男は、「会社=数字の集合体」ではないことに気づきました。
・利益が出ていても将来性がなければ評価されない
・社会の流れや技術が企業価値に直結する
これは、教科書では身につかない視点です。
さらに、「自分で選んだから、結果から逃げられない」という感覚を持ったことは、
責任ある意思決定の第一歩になりました。
次男(小学生高学年)|仕組みで考える力とリスク感覚
米国高配当ETFを選んだ次男は、
・分散するとリスクが下がる
・小さな成果が積み重なる
という投資の本質を、感覚的に理解しました。
一方で、「ドルの価値って毎日変わるんだね」と、為替リスクにも自然と気づいています。
これは「円で持っていれば安全」という思い込みを壊す、重要な学びでした。
長女(小学生低学年)|時間とリスクを身体で理解
長女が選んだのは、インデックス投資とハイリスクな国債(トルコ債)でした。
インデックス投資では、
・時間をかけると増えやすい
・今すぐ結果は出ない
という長期視点を学びました。
一方、トルコ債では、
「リスクに晒されてしんどくなるなら、リターンが高くても嫌」
と、リスクは感情にも影響することを実体験。
これは、大人でも経験せずに終わる人が多い部分で貴重な一次体験です。
「配当金で買うジュース」が金融教育の完成形だった
そして、ある日、配当金でジュースを買ったとき、子どもが言いました。
「これ、働かずに手に入ったお金だよね」
この一言で、お金=労働の対価だけではないという理解が完成しました。
同時に、
・元手があれば、また生まれる
・使っても、また戻ってくる
という資産形成の感覚も芽生えてました。
親が実感した、金融教育で一番大切なこと
この1年で分かったのは、
・正解を教える必要はない
・失敗を避けさせる必要もない
・「体験」を奪わないことが最重要
そういう意味でお年玉を使った金融教育とは、将来、自分で選び続けられる力を育てることに繋がるということを実感しました。
家庭で金融教育を始めるならSBI証券が現実的な理由
金融教育は、特別な教材がなくても始められます。
・少額から投資できる
・商品の幅が広く、学びを広げられる
・親が管理しながら一緒に学べる
我が家では、この条件を満たす環境として、SBI証券は非常にバランスが良い選択肢だと感じて子ども名義の口座を開設しましました。
まとめ|金融教育は「早すぎる」くらいでちょうどいい
金融教育に、早すぎることはありません。
・お金の正体を知る
・リスクと向き合う
・自分で選び、責任を持つ
これらは、社会に出てから身に付けさせようというのでは遅いです。
お年玉というチャンスを「消費」で終わらせるか、「一生使える力」に変えるか。
その選択を、ぜひ家庭でしてみてください。
SBI証券などのように利用しやすく各種手数料が安い証券口座を開設して親子で金融リテラシーを向上させてみてはいかがでしょうか。
筆者活動のご紹介
ここでは、筆者の活動をご紹介します。お力になれるものがありましたらお問い合わせフォームからご連絡ください。
ランキングに参加
現在、「にほんぶろぐ村」のランキングに参加中です。今回の記事に共感していただけましたら、以下の部分をポチっと押していただけますと、筆者の励みになります!
家計のご相談
筆者はファイナンシャルプランナーと簿記の資格を保有していて、家計管理や節約、簡単なライフプラン、お子さんへの金融教育などについての相談を受け付けています。
お問い合わせフォームからご相談ください。
電子書籍(kindle)の出版
このたび、我が家では、親子で挑戦した記録を電子書籍(kindle版)にして出版しています!
その書籍の一部をご紹介します!出版のご相談はご連絡ください。
「やってみな、わからん」M-1グランプリ1回戦突破の小学生兄妹コンビの挑戦記
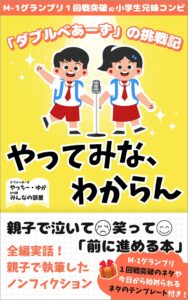
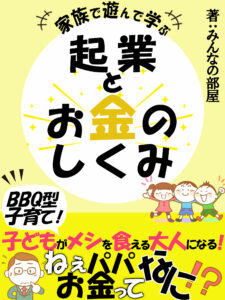
ウェブライターのお仕事の受注
筆者はウェブライターとしても活動させていただいております。もしお役に立てることがありましたら、お問い合わせフォームからご連絡いただけますと幸いです。
▼執筆経験のある主なジャンル
・金融系(お金の知識など)
・不動産系
・学習系(特に金融・法律)
・資格
・学校の紹介
・子供の教育
最後までご覧いただきありがとうございました。
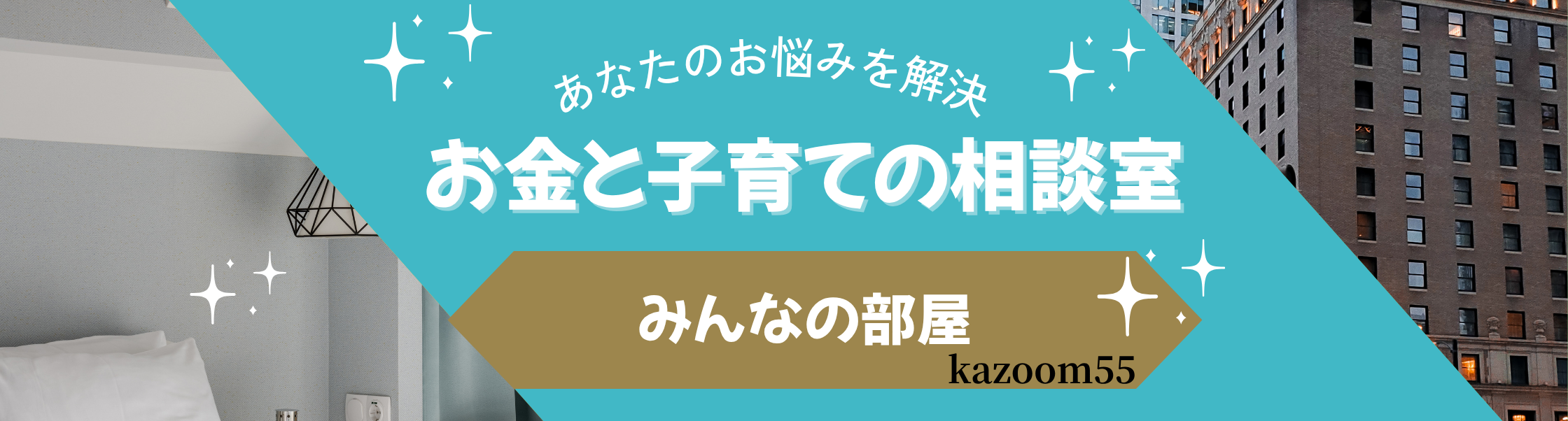




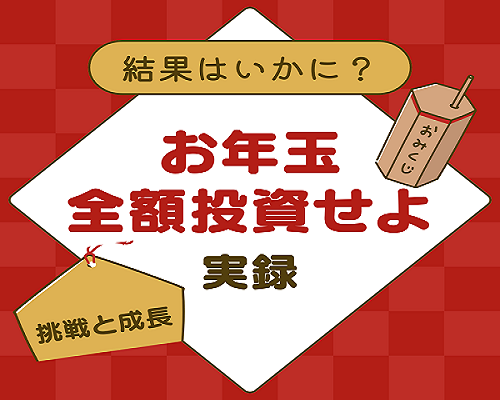


コメント