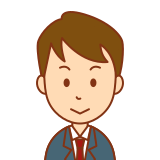
簿記の試験もネットで受験できるの?
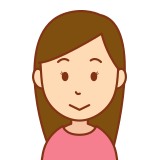
ネット試験の具体的な流れを事前に知っておきたい!
このようなことをお考えの方がおられると思います。
一生懸命勉強していればいるほど、当日の流れが気になります。
筆者は、先日、日商簿記3級のネット試験を受験し、何とか合格し、現在は子供たちが挑戦中です。
そこで、この記事では、筆者の体験したネット試験の会場での流れをご紹介します。
日常の勉強の成果を100%出し切るために、当日の流れを少しでもイメージしたいと思っている方は必見の内容です。
※本情報は、2024年時点のものですので、ご不明な点がありましたら、以下を参照してください。
「簿記」の試験は、ネット試験という方式があります。
日商簿記の試験には、ネット試験という形式で受験可能です。
ただ、ネット試験といっても自宅で受験できるわけではなく、あらかじめ自分で予約した日時にテストセンターへ出向き受験します。
受験の申込方法は、以下のとおり。
日本商工会議所のHPのネット試験の申込みをクリックして、説明文を読んで、株式会社CBT-Solutionの日商簿記2級・3級申込専用ページにアクセスして新規登録。
そしてCBT申込をしてあとは必要情報を入力します。
会場は、空いていれば、好きな曜日や時間帯や場所(テストセンター)を予約することができます。
受付~試験会場入室
当日は、開始30分くらい前に到着できるようにしましょう。
申し込んだテストセンターへ行って受付をします。
他の試験(例えば、英検、MOSなど)も同時に実施されていることもあり、混雑している場合があります。
ギリギリでも試験時間が短縮されるようなことはありませんのでご安心を。
「何時からの日商簿記試験で予約した〇〇です」と伝えると身分証明書証の提示を求められます。
必要な事項を記載している同意書の内容を確認してチェックし、日付と名前を書いて係員の人に提出します。
筆記用具は貸し出しがあるので、持ち込むことはできません。
ロッカーの鍵を渡されるので荷物を入れます(ロッカーには入れず自席の下に置くように案内が場合もあるようです)。
ポケットの中に物が入っていないことの確認を求められます。
ここで電卓の確認もあります。
ボールペンと白紙(ピンクや黄色などの色紙の場合もあるようです)2枚、IDとパスワードが書かれたプリントが入ったファイルを渡されます(試験後に全て回収)。
準備OKなら控室の指定された椅子で待機です。(→ここでトイレに行っておくのが無難かもしれません。)

試験会場入室から試験開始まで
係員の人が案内してくれた指定されたパソコンの前に座ります。
自習室のように1つ1つが区切られていて、横の人が何をしているかは分かりません。
余談ですが、私の試験会場では、真剣に猫の画像を選んでいた人がいましたが、なんの試験だったのでしょう。
席上には、防音用ヘッドフォンが置かれていました。(→使用したい人だけでOK)
何かあれば呼び出しボタン(居酒屋にあるような機器)で呼んで下さいと案内されます。
準備が整ったら、開始予定時刻より少し早くても受験可能です(私の場合には予約した時刻の20分くらい前でしたが受験できました。)。
まずは、渡されたプリントのID等を入力し、好きなタイミングで試験を開始できます。
「よ~い、はじめ!」のようなものはありません。
パソコンの操作には慣れているとは言え、普段のペーパーテストとは勝手が違うし防音用ヘッドフォンで無音の世界に入るのでちょっと焦るかもしれませんが、試験開始は自分の判断でできますから、ちょっと伸びをしたり、深呼吸したりして落ち着かせることができます。
電卓やマウス、下書き用プリントを定位置に置いて画面の注意文を読み、「試験開始」ボタンをクリック!!(ここからが時間のカウントになります!)
試験中
いよいよ試験が開始されました。試験時間は60分。
残り試験時間は画面上の下部に表示されます。
問題の詳細は公表することは禁じられていますので、残念ながらお伝えすることはできません。
第1問から第3問まであり、第1問の問題数は15問ありましたが、初心者の私でも正解できるくらい優しい問題が多かったです。
勉強不足な自分にとっては第2問目をチラ見したところ、すぐに解けそうになかったので、一番時間がかかるであろう第3問を先にやることにしました。
第3問は、貸借対照表や損益計算書、精算表の作成が出題されているようですが、私の場合は精算表の作成でした。
全体を通して、ネット試験だからと言って様変わりしてるわけではなく過去問と同じような感じの問題でした。
画面の下に残り時間が表示されているのですが、残り時間がどんどん減っていく状況に焦ります。
何とか1問目→3問目→2問目の順で埋めきってちょうど時間となりました(→見直す時間なし!)
試験終了後の流れ
時間が来たら強制終了になり画面が切り替わります。
結果は「印刷」ボタンをクリックして印刷します。プリンターは受付にあるので、荷物を持ってそこに移動します。
そして、その場で、点数と合否が出ます(ちょっと味気ない・・・)。
特に退室の案内などはありません。
貸し出された筆記用具やメモ用紙などを返却し、ロッカーの荷物を出して終了です。
ちょっとした注意点
試験はパソコン上で行われるので、勘定科目はプルダウンから選択することになります。
そして数字はテンキーで入力するのですが、場所によっては、勘定科目などの選択ができず直接入力する箇所があるので、注意が必要です。
また、「ここは入力する必要がありません」という採点の対象外というところもあるので、問題文を落ち着いて読むことが大事でした。
まとめ
慣れない試験形式ですが、これからの状況を踏まえると、こうした試験形式も増えてくるのではないでしょうか。
みなさんの合格に向けた勉強のお手伝いになれたのなら幸いです。

おまけ
このたび、我が家では、子供へのお金の教育について実践した模様を電子書籍(kindle版)にして出版しました!その書籍がこちらです!
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XVHJ5P7/ref=cm_sw_r_tw_dp_7RMX4CK1SNP1KRGC1ZFP
我が家で行った家庭内起業の模様をまとめたものです。お子さんのマネーリテラシーを向上させたい方は必見です。
また、実は、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、以下の部分をポチっとお願いします。筆者の励みになっています!
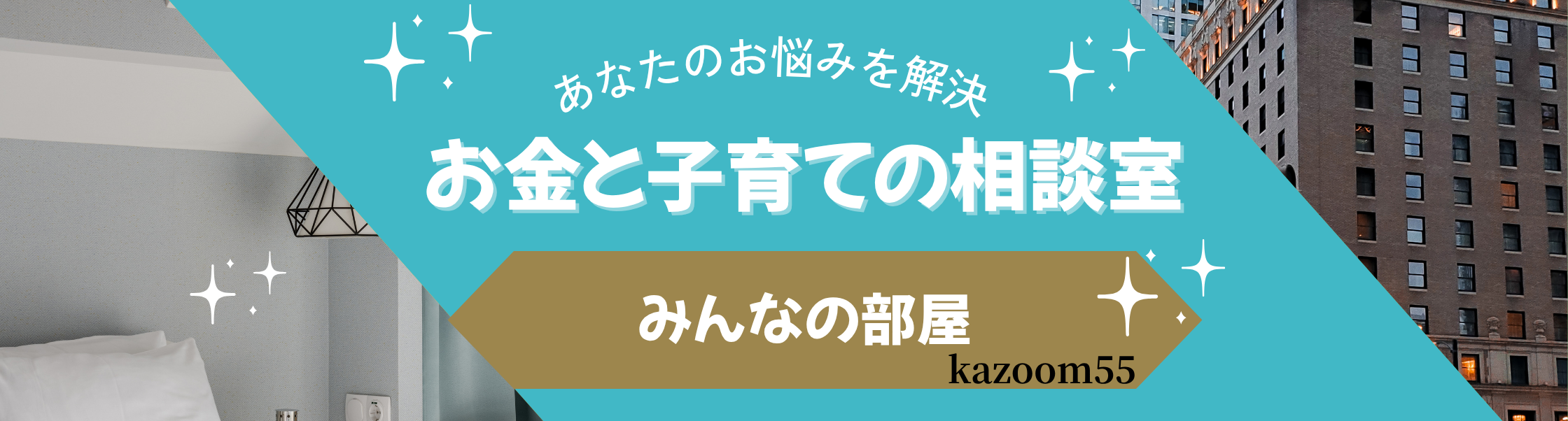




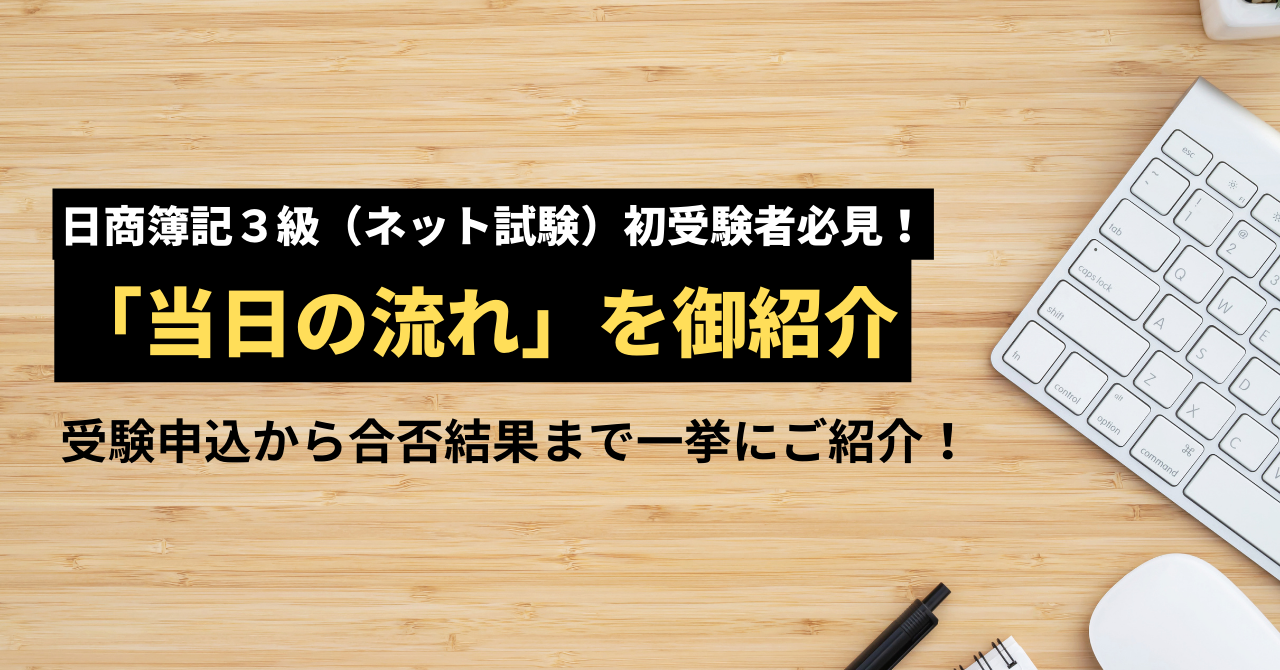


コメント