この記事では、保険の見直しをして年間20万円以上が節約できた我が家の行動をご紹介します。
今回の行動の準備については、是非前編の記事を参考にしてください。
我が家の家族構成は?
我が家の構成は以下のとおり(当時)
3人の子供(中2、小2、年長)がいる5人家族で、年齢は夫婦共に40代。
家計は、収支がトントンな状態で貯蓄も満足にできない状態。
これから「控える長男の受験や老後資金の蓄えのためにそろそろ家計を見直すかな」と思い、家計簿を確認したところ。
保険料が占める割合が多い!

このころの我が家は、「不安は全て保険で備える」姿勢。
そこで、前編でも触れたように、社会保険なども踏まえて、「低確率で発生するもので、発生したら金銭的に大打撃を受けるもの」についてのみ保険で備えるという方針に転換しました。
見直し前に加入していた「保険」と「保険料」は?
見直し時点で加入していた生命保険等は以下のとおり。
- 死亡保障5000万円(三大疾病特約)
- 死亡保障2500万円(三大疾病特約)
- 医療保障 月額1万円
- 収入保障 月額20万円(就業不能特約付き)
- 養老保険
- 団体信用保険(住宅ローン契約時)
保険料は、1~4で、月額約3万円(年間36万円)、5は一時で支払い済みという状況でした。
各種保険をどう見直したか?
ここからは、これらの保険をどのように見直したかについてご紹介します。
各保険別に「見直す前の状況」(ビフォー)と「見直した理由・結果」(アフター)に分けて、ご紹介します(赤のアンダーラインは見直しポイントです。)。
死亡保障保険について
- 死亡保障5000万円(三大特約)※夫
- 死亡保障2500万円(三大特約)※妻
見直す前の状況
職場の団体保険で、死亡したら保険金が支払われるオーソドックスなものです。
子供が3人生まれたこともあり、何となく保険金額が多い方がいいかなと思いつつ加入。
また、妻分についても、保険金額が高い方が安心できるんじゃないかとの理由で、保険料をあまり気にせず、加入。
そして、生命保険金は、何も考えずに保険金の受け取りは一括を選択していました。
見直した理由・結果
結論としては、1は維持し、2は大幅に減額(2500万円→500万円)
我が家の場合、万が一のことがあった場合には、遺族年金が支給されることになり、大体の金額(我が家には、18歳未満の子供が3人いる間の加算の金額)も分かりました。
そこで、月々の支出と支給額を比較し、保険では足りない部分を保険で補うことにしました。
そして、夫婦のどちらかが死亡した場合は、もう片方は稼働することはできるので、保険金額は大幅に減額することに。
支払方法については、我が家の今後(高校や大学の授業料などの急な出費があったり、家電などの故障、子供の結婚資金)を考えたときには、一時金で一部を受け取り、残りは分割で受け取る、併用する方法が最適だと思い、この方法に変更。
医療保険について
医療保障 月額1万円
見直す前の状況
これも職場の団体保険で何となく、入院したらお金がもらえるといいなということで加入。
入院生活を快適にした方がいいなと思ったのと、医療保障があった方が早く病気が治るような気もしていました。
見直した理由・結果
解約。
治療費については、高額療養費制度があり、我が家の場合は、最大で月10万円程度の負担で済むことが分かりました。
入院期間にもよりますが、万が一入院することになった場合には、まずは有給休暇を消化することになり、その間は給料は支払われます。
とすれば、貯蓄もあるので、入院費を支払うことができないということは想定できないので、金銭的に大打撃が加わることは少ないと判断。
また、入院がある程度、長期化した場合であっても、傷病手当(給料の3分の2)、その後は、障害年金が受け取れます。
また、そしてこの保険は、自宅療養中は適用されないので、我が家ではこの保険を利用する場面は少ないと判断しました。
収入保障保険(就業不能特約付き)
収入保障 月額20万円(就業不能特約付き)
見直す前の状況
自宅を購入する際にライフプランを立ててもらった生命保険会社の担当者に勧められて入りました。
収入保障保険とは、一言で言えば、生命保険の分割払いで、年齢が進むにつれて、段階的に保険金の金額が減る変わりに保険料が通常時より安価というものです。
支払方法が異なりますが、単なる生命保険。
そして、実はこの保険が我が家の全保険料の半分を占領!!
高いな~と思っていましたが、まあ、担当者にはライフプランを任せているしお世話になっているし・・・という人情的な理由で保険を継続していました。
見直した理由・結果
解約!
収入保障保険とは、一般の死亡保険とは支払方法が違うだけなので別に生命保険に入っている我が家では二重に生命保険に入っていたということになります(くすん。)
また、この保険には就業不能特約がついていますが、身体的な理由(要介護認定)のみに限られるとのことで精神疾患(うつ病など)で入院したり自宅で療養したりしているときには対象外でした。
ちなみに40代の休業の約半数は精神疾患だそうですが、精神疾患に対応していない就業不能保障保険が多いようです。
メンタル不全で働けなくなっても保険ではカバーされない!
つまり、保険料は多額なのに、我が家には入る価値のない保険でした。と、いうことで即刻解約!
養老保険について
死亡保障130万円(払い込み済み103万円、解約返戻金105万円)
見直す前の状況
自宅を購入した際にライフプランを立ててもらった生命保険会社の担当者に勧められて入りました。
子供の教育資金として、貯金していたのですが、それを寝かしておくよりも養老保険にしましょう、解約返戻金は元本を超えますので大丈夫です、と言われ入りました。
見直した理由・結果
再度、担当者に解約返戻金を算出してもらったところ、元金を超えていたのと、このお金は将来の長男の学費にという目的がはっきりしているものだったので、とりあえず今回は維持することにしました。
しかし、貯金は貯金、保険は保険にしておかないと、解約返戻金が元本を割り込んでしまうことはあります。まさに「混ぜるな、危険」です。
その他→新たに【就業不能保険】に加入
精神疾患(うつ病など)で入院したり自宅で療養したりしているときには我が家では保険金が受け取れる状況にはなっていませんでした。
また、調査の結果、40代で1番多い休業の理由は「精神疾患」です、周りにも休業している人はたくさんいます。
そして、今の家族構成では、教育費がかかりだすときに、身体的にせよ、精神的な理由にせよ、万が一のことがあり働けなくなった時には、給料としてもらえるべき金額がなくなり、生活に直接打撃が加わってしまいます。
「低確率で発生するもので、発生したら金銭的に大打撃を受けるもの」についてのみ保険で備える。
そこで、就業不能保険に加入することにしました。
また、保険料をできるだけ抑えるべく、傷病手当が受給できる期間は、保険金を半分に抑制し、傷病手当が切れる期間に満額受け取るというマニアックな契約をしましたw

保険担当者との連絡
保険は見直したいなと思っていても、顔なじみの担当者に直接言いにくかったり、逆に丸め込まれて更新や新たな保険を進められることもあるかもしれません。
そこで、我が家では次の方法で解約をしました。
- 会ったり、電話でのやりとりはしない
- はっきりメールで断る
- すぐ処理する
保険の販売員の方たちは百戦錬磨の人たちなので、直接会ったり電話でやりとりをすると丸め込まれるかもしれないので、多忙を理由にメールのやりとりだけとしました。
「またライフプランを立てさせていただきましょうか」「ズームでも相談できますよ」というメールが送られてきましたが、「既に他の保険に入ったので解約します、ひとまず解約請求書を送ってください。また何かあればご相談させていただきます」ときっぱりと返信しました。
また、ぐずぐずしていると、「この前の件ですが」と連絡をする口実を与えることになります。解約するときは一気に行うことをお勧めします。
私の場合は、解約請求書の電子データが送られてきてから5分で提出しました(笑)
保険の見直しで年間20万円以上節約に成功!
このような行動の結果、保険料が月額3万円から8000円に減額しました。
つまり、年間約26万円、30年で780万円の節約となりました。
さらに効果を分析すると、例えば、投資で年間で26万円の配当を得ようとしたら3%の運用で約860万円以上必要ということになります。
それくらいの効果が今回の見直しにはあったということになります。
まとめ
前編と後編に分けて、実際の我が家の保険の見直しをするまでの具体的な行動をご紹介しました。
保険を見直す際には、
- 社会保険の保障がいつまでにどれだけ支給されるのか
- 今後世帯としてどの程度のお金がいつ必要となるのか
- 貯金でカバーできるのはどこまでか
を数字だけで分析する(感情論を抜きにする)ことが大切です。そして。
- 解約は一気に行う
お金音痴な私が、ここまで見直しできたということは、この記事を読まれた方なら誰でもできる節約術だと思います。
ぜひ、面倒がらずに、今度の休日にでも保険の見直し家計改善に取り組まれてはいかがでしょうか。
おまけ
お金に関する本や情報源を参考にすることで、より深くお金のことを学ぶことができます。ここでは、おすすめのお金に関する本や情報源を紹介します。
まずは、お金に関する本でおすすめなのは、なんといってもこの本になります。この1冊があれば、一生お金に困らない5つの力を身に着けることができます。画像をタップすると購入画面になります。
このたび、我が家でも、子供たちとお金にまつまる電子書籍(kindle版)を出版しました!その書籍がこちらです!

我が家で行った家庭内起業(ごっこ)の模様をまとめたもので、親子で実践できる内容になっていますので、是非お読みください♪
また、実は、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、ポチっとお願いします。すっごく励みになります♪
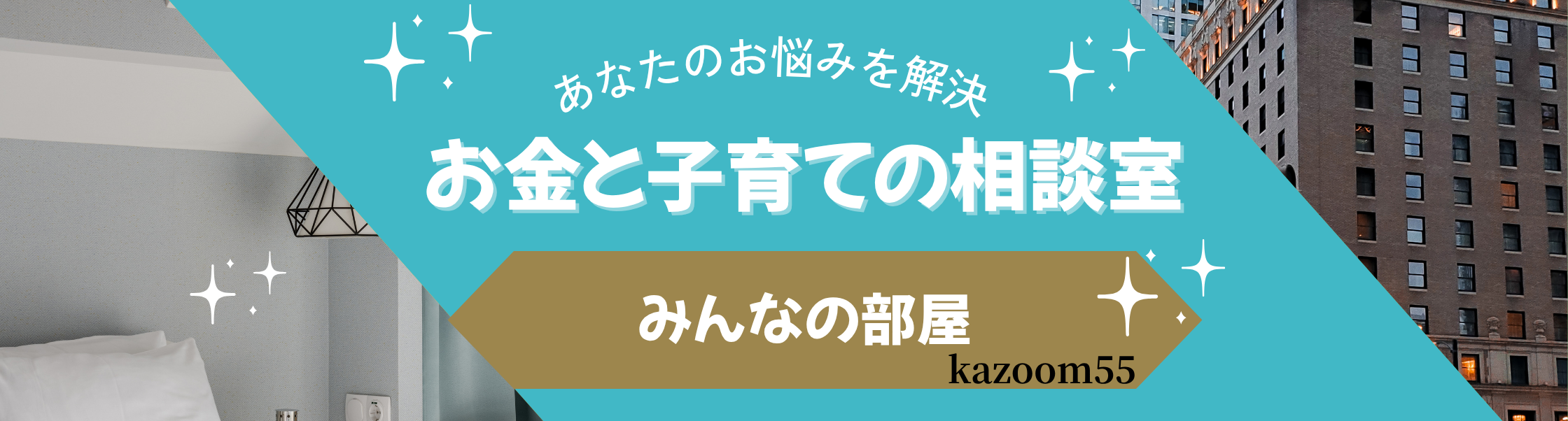









コメント