物語を知ったきっかけは「ユダヤ人」に関する本でした。
お金は生まれてから死ぬまで使う道具ですが、「お金」に対することは学校で教えてくれません。
そこで、筆者は数年前から子供たちにお金の教育をしています。
海外に目を向けると、「お金」儲けの考え方に優れているのは、ユダヤ人です。
「ユダヤ人」とされている人の中には、実は、超有名な心理学者や経済学者、映画監督やグーグルの創業者やフェイスブックの創業者などが、たくさん含まれています。
そんな「ユダヤ人」には大切している物語がいくつもあって、それを基に子供と会話することで金融教育を行っています。
筆者も「ユダヤ人」の方々にあやかりたいなと思っていたところ、一冊の書籍を見つけました。
それがこちらです。この本に収録されている物語について子供たちと話をした内容をご紹介したいと思います。
是非親子でこの物語をお読みいただけると嬉しいです。
「難破船と3人の乗客」というお話
ある時、乗客を乗せた船が嵐にあって、難破(遭難)してしまいました。

嵐の中で方向が分からず、高波にも襲われたため、船の一部が壊れてしまいました。
しかし、何とかある無人島にたどり着きました。
その無人島は、美味しそうなフルーツがたくさん実っている島。
船は、その島で修理を済ませてから、ただちに出航することになりました。
この間に3人の乗客は、さまざまな行動をしました。
1人目の乗客は「船に留まった」
1人目の乗客は、「いつ修理が終わるか分からないので、もし出航する時に、無人島に取り残されては大変だ」と思いました。
そして、船から一歩も出ずに、ずっと船に留まることにしました。
嵐に遭ってから何日もご飯を食べておらず、かなり空腹。
ただ、船から出て取り残されることの方が心配だと思って、じっと我慢していました。

2人目の乗客は「近場でフルーツを食べた」
2人目の乗客は、島に降りることにしました。
そして、船の修理が終わったらすぐに戻れるように、船が見える範囲内でフルーツを食べることにしました。

そして、船の修理が終わる様子を見て、急いで走って船に戻ってきて、何とか船に乗ることができました。
フルーツをお腹一杯は食べられませんでしたが、なんとか空腹は満たされました。
フルーツを食べたことで、水分補給もできました。
3人目の乗客は「島の奥でフルーツをお腹いっぱい食べた」
3人目の乗客は、「簡単に船が修理されることはない」と思って、無人島の奥の方まで入っていき、フルーツをお腹がいっぱいになるまで食べました。

船が見えない島の奥地まで入り込んでしまっていましたが、さらに奥の方には、とても美味しそうなフルーツが、まだまだたくさん実っていました。
そこで、3人目の乗客は、島の奥の方へどんどん進んで行き、フルーツをお腹いっぱいになるまで食べ続けました。
そろそろ船に帰ろうかと思って、戻って見ると、船は出航した後で、無人島に取り残されてしまいました。
3人の乗客の結末は?
全く船を降りなかった1人目の乗客は、無人島に取り残されることはありませんでしたが、空腹でその後の航海に耐え切れずに、死んでしまい目的地まで行くことはできませんでした。
また、島に取り残された3人目の乗客は、空腹にはなりませんでしたが、結局、無人島から出ることはできずに、一生がそこで終わってしまい、目的地まで行くことはできませんでした。
結局、航海を終えて、生きて目的地に到着することができたのは2人目の乗客だけでした。
この物語の教訓 適正なリスクを取ることが重要
今回のお話では、船が出ることを恐れすぎて一歩も出なかった乗客も、逆に船はそう簡単に出ないだろうと思って島に取り残された乗客も不幸な結末に。
このお話の教訓は、「適正なリスクをとることが大事」ということです。
この物語は、リスクに対して、あまりにも慎重すぎても良くないし、楽観視もあまりよくないことが分かる物語です。
何らかのリターン(結果)を得ようとするのであれば、それ相応のリスクを取るべきで、重要なのは、そのリスクが、今の自分に適正なものとして許容できるかという判断ができるかということです。

そのためには・・・
「どれくらいのリスクがあるのか」
「それに対して得られるものがどの程度あるのか」
「両者はバランスが取れているか」
を分析する必要があるということのようです。
今回の物語でいうと「どこまでいけば食べられるフルーツの量はどれくらいか」「船が勝手に出航してしまうかもしれない不確実性がどれくらいか」「もし発生したらすぐに戻れるか(フルーツを食べることをやめて船に戻れるか)」ということを「正確」に認識していたかがポイントです。
子供たちの反応はどうだった?
筆者の子供の反応はどうだったか?をご紹介します。
「この物語の感想は?」という質問をしたところ・・・
長女「死んじゃった乗客かわいそう、なぜ分からなかったのかな・・・」
次男「2人目の乗客が、フルーツを少し持って帰ってきてあげていれば、1人目の乗客を救えたんじゃないか」
長男「船長にフルーツを取ってきてあげるから戻ってくるまで出航を待っていてほしいと、あらかじめ頼んでおいて、できるだけ食べて、できるだけ持って帰ってくるようにした方がいいんじゃないか」
などという回答でした。
三者三様でしたが、この物語の教訓以外にもチームで対応することの強さなどを知ることができたようです。
また他人と協力することによりリスクが低くなることがあるということも。
筆者の子どもたちも3人力を合わせて、お金に困らない豊かで自由な人生を送ってもらいたいものです。
●今回、参考にした書籍について、詳しくお知りになりたい方は、こちらからどうぞ。
楽天:ユダヤ人の成功哲学「タルムード」金言集 [ 石角完爾 ]
Amazon:ユダヤ人の成功哲学「タルムード」金言集 (集英社ビジネス書)
●他の記事はこちらからどうぞ!

このカテゴリーでは、学校や社会で教えてくれない、だけど生きていくために必ず必要な「お金」のことについて記事にしています。親子で楽しく学べる「おまけ」も記事にしています。
おまけ
筆者は、この記事でご紹介した物語などを通して家庭内でのお金の教育を進めています。
このたび、我が家では、子供へのお金の教育について実践した模様を電子書籍(kindle版)にして出版しました!その書籍がこちらです!
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XVHJ5P7/ref=cm_sw_r_tw_dp_7RMX4CK1SNP1KRGC1ZFP
我が家で行った「家庭内起業」の模様をまとめたものです。
お子さんのマネーリテラシーを向上させたい方は必見です。
また、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、以下の部分をポチっとお願いします。筆者の励みになります!
今回は、以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。
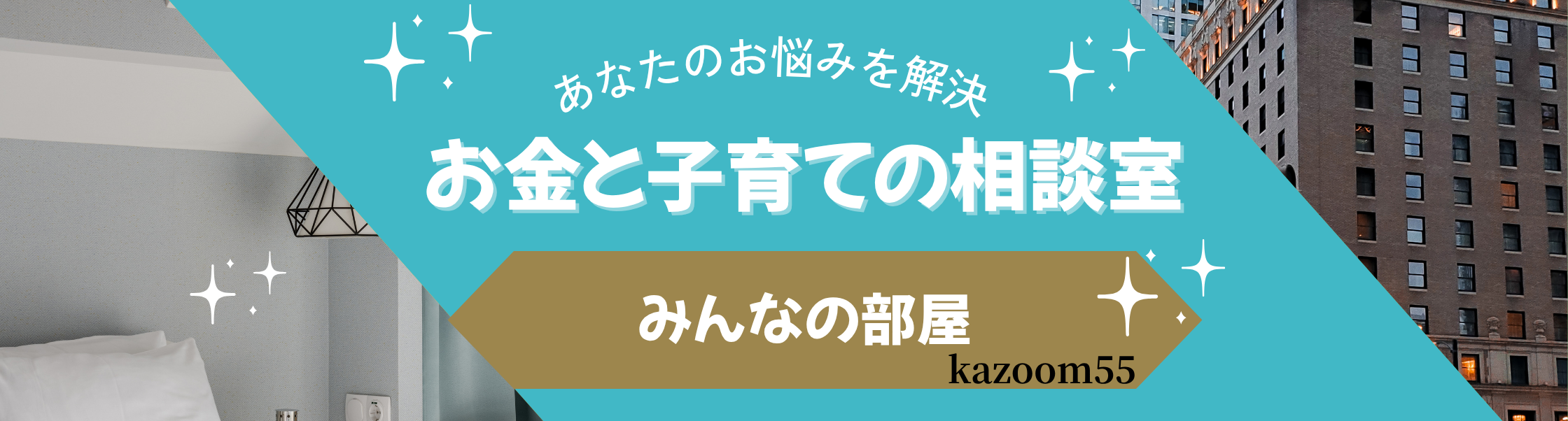



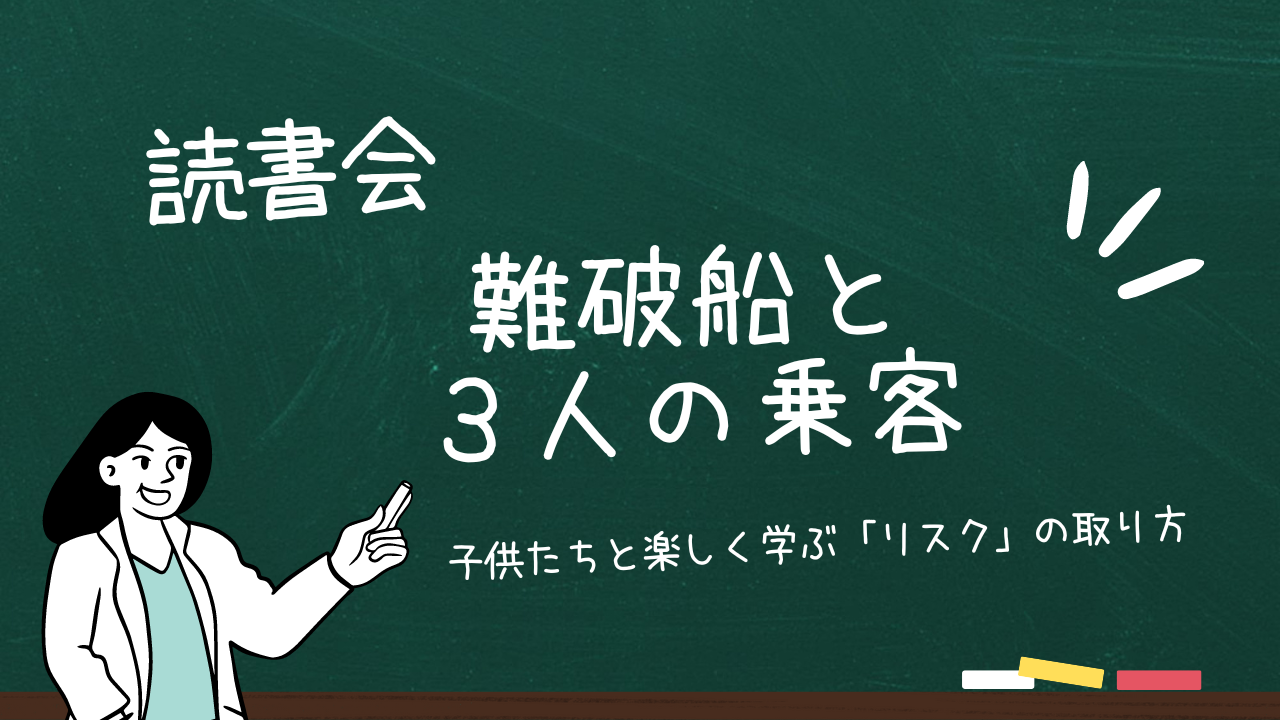
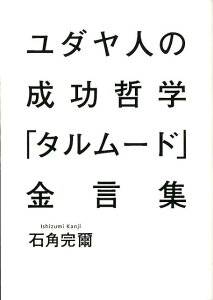
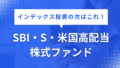
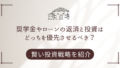
コメント