「人間50年」ではなく、現代は、「人間100年時代」。
そんな中で、2019年の金融庁の報告書で話題となった「老後2000万円問題」。
「年金だけでは、老後は2000万円不足します」と国に言われても。
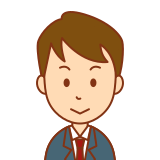
日々の生活で必死で、2000万円も用意できないよ~?
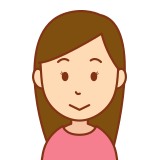
投資って言われてもなんだか怖いよ~?
こんなお悩みの方もお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今後寿命が延びるにつれてこのようなお悩みを持った人は増加すると思われます。
そこで、今回は、そんな方のお悩みを解決する1つの方法をご紹介します。それは。
「iDeCo(イデコ)」
この記事では、NISAと並んで、老後資金の切り札となる「iDeCo(イデコ)」をご紹介します。
- 「iDeCo(イデコ)」とは何なのか?
- 「iDeCo(イデコ)」は、なぜ老後資金対策となるのか?
- 「iDeCo(イデコ)」で老後資金を確保できるのか?
- 「iDeCo(イデコ)」には、デメリットはないのか?
この記事を読めば、そんな疑問が解消され、老後2000万円問題のお悩みを解決するヒントが分かります。
【iDeCo(イデコ)】とは、自分で作るオリジナル年金
「iDeCo(イデコ)」というのは、特定の金融商品の名称ではありません。
自分のために年金をつくるための制度です。
個人型確定拠出年金の英語から作れた造語です。

事前に決めた掛け金を積み立てていき、投資などで運用するので、年金受取額は運用成績によって変わります。
運用がうまくいけばいくほど、老後の年金受取額も増えるというわけです。
日本の年金制度は3階建てになっています。
- 1階部分が国民年金でこれ全員が加入してます。
- 2階部分は厚生年金会社員や公務員が加入します。
- 3階部分が私設の年金である「iDeCo(イデコ)」です。
年金の平均受給額は、国民年金の平均受給額は5万6000円、厚生年金の平均受給額は14万6000円(国民年金を含んでいる額)。
公的年金だけで老後を生活していくのでは厳しい。

そこで、政府は「iDeCo(イデコ)を活用できる人を増やす法改正をするから自分の老後には自分で備えてください」と、この制度が開始しました。
【iDeCo(イデコ)】が老後対策になる理由は、ズバリ「節税」!
老後生活を年金だけ送るのは厳しいということは分かりましたが、iDeCo(イデコ)を使うとなぜ、老後対策になるのでしょうか。
その答えは、「節税」です。
iDeCo(イデコ)には、多くの節税メリットがあります。以下、ご紹介します。

その1 掛け金が全額所得控除になる。
「掛け金」の拠出時に所得控除になります。会社員や公務員の場合であれば、年末調整時に申告すれば、所得が控除されます。
「iDeCo」では、掛け金×税率の分だけ所得税住民税が安くなります。
例えば、所得税率10%、住民税率10%で掛け金の合計が800万円だった場合、約160万円もお得に。
その2 運用益には税金はかからない。
通常の株取引や投資信託の売買の場合には、売却益や配当金利息などの運用益には約20%の税金がかかります。しかし。
「iDeCo(イデコ)」では運用益は非課税。
例えば、運用益が200万円の場合、約20%にあたる40万円は税金で差し引かれます。
しかし「iDeCo(イデコ)」の運用益は非課税になるので、200万円全額を得ることができます。
その3 受領する時にも節税になる。
「iDeCo(イデコ)」で運用した資産を受け取る時には、公的年金等控除、退職所得控除といった税負担を軽減する制度を利用することが可能になります。
取得したり運用したりする時だけではなく、受領するときも節税になるのは、大きなメリットです。

【iDeCo(イデコ)】には、こんなメリットもある!
「iDeCo(イデコ)」の最大のメリットは上記のように「節税」にありますが、この他にもiDeCoには以下のようなメリットがあります。

その1 自動的に積み立てできる
天引きや引き落としにより着実に積み立てられ、掛け金は自動的に確保されます。
貯蓄が苦手でついつい使いすぎてしまう人も着実に資産形成ができます。

その2 投資商品が厳選されてる
通常投資商品は無数にあり、中には詐欺的な商品やリスクが高すぎる商品なども含まれていますが、「iDeCo(イデコ)」が使える商品はかなり厳選されています。

そもそも年金を補う制度ですから、それに適した対象商品に限定されています。いわば政府お墨付きの商品です。
投資初心者でも、商品選びで悩まずに安心して購入することができます。
その3 差押禁止財産である
例えば、ローンが返せなくなったり、借金が返せなかったりした場合には、自宅などの不動産や給料などの一部が差し押さえられることがあります。

しかし、「iDeCo(イデコ)」は、法律上、差押えが禁止されている財産です。
将来、万が一経済的に自信が困窮することがあっても「iDeCo(イデコ)」で運用している財産は差し押さえられません。
その4 転職時にも持ち運びが可能
iDeCo(イデコ)は、持ち運びが可能です。

会社員の方が転職した場合、転職先に企業型の確定拠出年金があれば、そこに運用資産を移管することができます。
この時に積み立てたお金が無駄になってしまうこともありませんし、課税されてしまうこともありません。
【iDeCo(イデコ)】で老後資金を確保できるのか?
このようにメリットが多い「iDeCo(イデコ)」ですが、老後までに「2000万円」を確保することは可能でしょうか。
例えば、会社に企業年金のない会社員を想定します。
毎月2万3000円を30歳から60歳の30年間拠出したと想定します。続けて年5%で運用できたら60歳時点での資産額約1900万円(元本828万円)になります。

確実に毎年、年5%で運用できる保障はありませんが、計算上は、「老後2000万円問題」の大部分を解決できる可能性があります。
【iDeCo(イデコ)】のデメリットは?
では、このようにメリットが多い「iDeCo(イデコ)」にもデメリットがあります。
その1 長期間資金が拘束される

一度拠出したお金は、原則、60歳以降にならないと引き出せません(10年以上掛けている場合)。
例外的に中途解約が認められる条件もありますが、その条件を満たせる人はほとんどいないと思います。
その2 元本割れの可能性

iDeCo(イデコ)の対象商品の中には、元本が保証されている定期預金などの商品のほかに、投資信託が多くあります。
株や債券など元本割れの可能性がある以上、マーケットの状況によっては元本割れする可能性があります。
確実にノーリスクで安全に資産が増えるというものではありません。
その3 手数料がかかる
加入口座開設などを行った時、掛け金を納付した時、年金を受け取る時などに国民年金基金連合会、運営管理機関、事務委託先にそれぞれ手数料を支払う必要があります。
このうち、運営管理機関や事務委託先の手数料はどこの金融機関で口座を開設するかによって変わってきます。
その4 受領時に節税になるかは状況による
iDeCo(イデコ)が本当に節税になるかどうかはこれは人によります。

掛け金の拠出時には、メリットとしてお伝えしたように所得控除もあり運用益が非課税です。
しかし、運用した資産を受け取るときは課税対象となります。
公的年金等控除とか退職所得控除が使えることは、ご紹介しましたが、あくまで税負担を軽減する措置であり必ずしも税負担をゼロにするものではありません。
それに、他の収入なども踏まえることになりますので、いろいろ受け取り方やタイミングを工夫する必要がある人もいます。
まとめ
今回は、老後の強い味方「iDeCo(イデコ)」についてご紹介しました。
国が推進するほどのメリットも多い制度ですので、資産形成の選択肢に組み入れてみてはいかがでしょうか。
また、「iDeCo(イデコ)」は2001年から開始された制度ですが、2022年に改正がされていますので、こちらもご確認ください。
また、「iDeCo(イデコ)」と同様に節税のメリットを得られるNISAについても以下の記事で分かりやすくまとめましたので是非参考にしてください。

おまけ
このたび、我が家では、子供とのお金の勉強をテーマとした電子書籍(kindle版)を出版しました!その書籍がこちらです!

勤労感謝の日に我が家で行った家庭内起業の様子とお金の勉強をするにあたってのポイントをまとめたものです。
将来のお子さんの選択肢を増やすために有用な一冊です。是非読んでいただけると嬉しいです。
また、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、下の部分をポチっとお願いします。すっごく励みになります♪
今回は、以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。
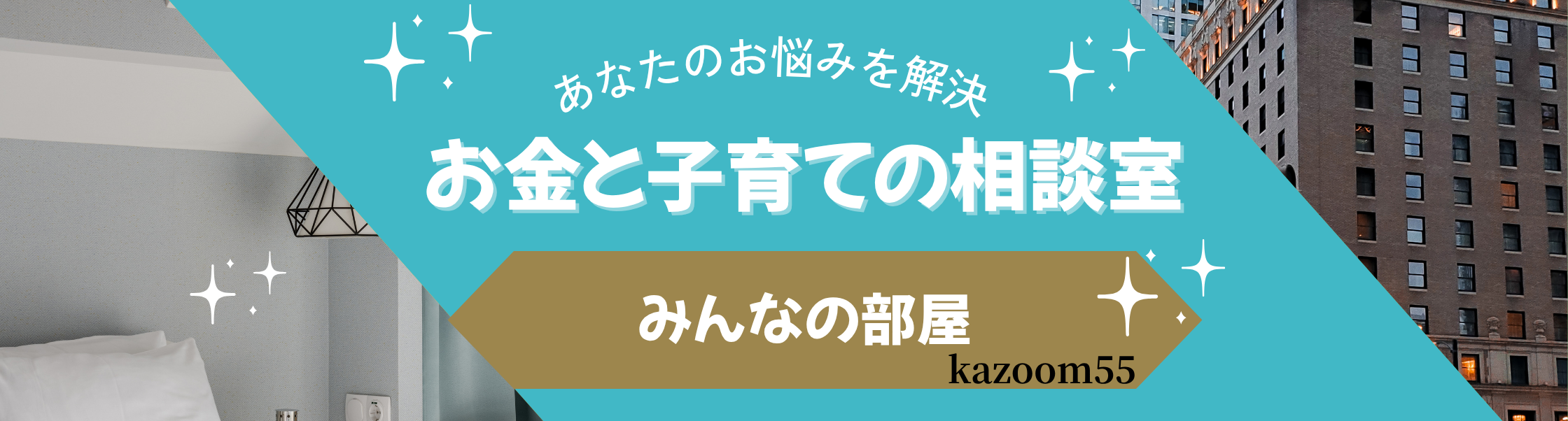







コメント