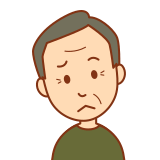
買い物をすると、ついつい買い過ぎてしまうんだよな~
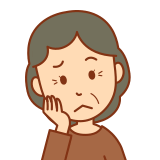
買い物をすると、いつも同じ商品を買ってしまうわ~
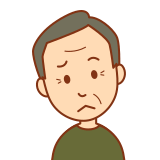
資格試験の勉強を辞めようかと迷っているんだけど、今までかかった費用が持ったないないし辞められない・・・。
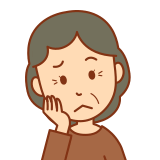
「タウリン1000mg配合!?」たくさん入っているわね!
買おうかしら?
このような経験をした方も多いのではないでしょうか。
筆者も何だか気が付かないうちに、予定よりもたくさん買い物をしてしまって、家計が苦しくなった経験もあります。
「気を付けているのに、自分の意識が低いのかな・・・」
そんなことを思ったりしたこともありました。
しかし、実は、自分の意志で普段から多くの決断を繰り返しているように思っていますが、実は「選択させられている」ことがあるんです!
人間も動物。
「とりがちな行動(習性)」があり、ある条件が整えば、ついつい私たちは無意識に、その行動をとってしまいます。
買い物などはその典型例。
実は、これを逆手にとって、会社やお店は、日常生活における私たちがとりがちな行動(習性)を分析して、いろいろ物やサービスを販売し、私たちはそれを買っていた・・・。
筆者はそのことに気が付いたおかげで、買い物をするときに慎重に判断することができ、浪費をしなくなりました。
この記事では、お金を使う場面での私たちがとりがちな行動(習性)をご紹介します。この記事を読んていただき、浪費しがちな場面を知ることで、無駄な出費を抑えられるかもしれません。
では、ご紹介します。
習性その1 「人は過去の記憶から」モノを選ぶ
誰しもお気に入りはありますよね。
レストランでメニューを選ぶ時やスーパーでお菓子を買う時など、ついつい過去の記憶から「いつも同じモノ」を選びがちな習性があります。

買い物をする時など、決断する場合には、過去の経験が考慮されます。
過去に選んでよかったもの無意識に選んでいます。
そこで、販売者側は、こう考えます。
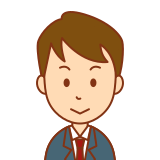
何とか自社の商品を買い手の記憶に残したい!
例えば、日本マクドナルドの創業者である藤田田(ふじたでん)さんは、「人間は12歳までに食べてきたものを一生食べ続ける」と考えて、子どもたちをターゲットにハンバーガーを売りまくりました。
子どもの記憶に商品を残すためです。
なぜなら、「人は過去の記憶からモノを選ぶ」
その人は、幼少期から、なじみがあるマクドナルドに来てくれるし、もしその人が、親になったら今度はその子供をマクドナルドに連れてくる、そうすると、その子供も味を覚えてもらえます。

それが、また繰り返される・・・。
マクドナルドの無限ループですw
このため、マクドナルドは世代を問わず、国民的な常連店になっています。
人は記憶に残っているものをついつい選んでしまうという人間の習性を見抜いた戦略といえます。
習性その2 「人は見たことのあるモノ」を買ってしまう
見たことのあるAという商品と初めて見るBという商品だとどちらを選びますか?
人間には見たことがあるもの、「知っているモノをいいものだ」と信用する傾向があります。
こういう習性から、CMで見たりネット広告で見たり、街中で見た広告の商品を、つい買ってしまうことがあります。
これを販売者側はこう考えます。
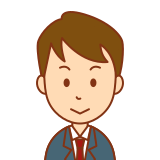
とにかく自社の商品を知ってもらい認知度を上げたい!
販売者側からすれば、まずはお客さんに知ってもらうことを大切にしています。
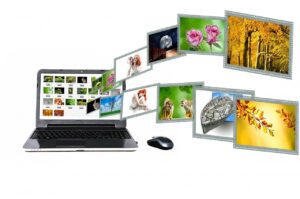
例えば、CMをたくさん打ったり、試供品やサンプルなどを配布して知ってもらうことを積極的にやっていますよね。
通勤時間に何気なく見ている広告や手渡される試供品にもこういった目的があるのです。
習性その3 「人は未来よりも今の利益を優先してしまう」
例えば、Aは「1万円をもらえる道」Bは「1年後に2万円をもらえる道」があったとした場合、どちらを選ぶ人が多いと思いますか?
合理的に考えて、得なのは、1年後に2万円をもらえるBの道のはずです。
しかし、ほとんどの人は、今すぐに1万円をもらうAを選ぶそうです。

人間には、今すぐに手に入る楽しみに大きな価値を見い出す習性があり、目の前の小さな利益に我慢できません。
昨今では、投資がブームになりつつあります。
長期投資よりも短期投資が人気があるのは、このためです。

しかし、本来「投資」は、今の小さな利益を先送りにして後で大きな成果を手に入れる方法です。
短期であればあるほど、リスクが高くなってしまいます。
結果、投資で失敗する人が多いようです。
投資は自分をコントロールしないといけない理由は、ここにあります。
習性その4 努力が無駄になるのが嫌だから損をするのにやめられない
例えば、オンラインゲームのガチャに1000円を使ったとします。
なかなか目当てのアイテムをゲットできなかった場合、「すでに1000円使ったのだから引くに引けない」と思って、さらにお金を使ってしまうことがあります。

実は、人間には、「ここで止めてしまうと、これまでの時間やお金が無駄になる」と思って、なかなかやめられないという思い込みが働くことが多いです(サンクコスト効果といいます)。
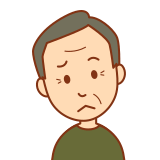
資格試験の勉強を辞めようかと迷っているんだけど、今までかかった費用が持ったないないし辞められない・・・。
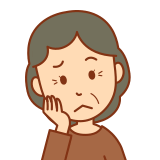
ギャンブルで負けが込んできてるけど、ここで止めたら今まで使ったお金がもったいなくて止められない・・・
いわゆる「損切り」が出来ず、結果として大損することになります。

サブスクなどの継続的なサービスや商品購入などでお金を使うときには、あらかじめ使う金額や撤退する条件をあらかじめはっきりと決めておくことが大切です。
習性その5 表現の仕方で行動が変わる
人間は、「同じことを言っていたとしても、表現の仕方次第で、受ける印象や行動が変わる習性」があります。

例えば、「タウリン1000mg 配合」と聞いて。
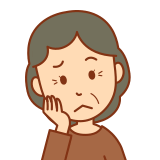
「タウリン1000mg配合!?」たくさん入っているわね!
買おうかしら?
実際は、「1g」なのですが、このように数値を変換することでたくさん入っているような印象を受けます。

販売者側よく、1980円や999円などのように末尾が中途半端な値段を設定しているのも、お得な感じを印象づけるためです。
このように販売者側は、相手の心を動かしやすい表現を日夜研究しています。
習性その6 追い込まれると理性的な判断ができなくなる
人間は、追い込まれると理性的な判断ができなくなる傾向があります。
例えば、人はボロボロに負けている状態だとギャンブルに出る傾向があります。

借金がある人とかそもそも貯金が少ない場合は、冷静さを失い、夢を見て一か八かの勝負に出やすくなります。
その逆で、富裕層の人があまり宝くじを買いません。

販売者側では、こういった習性を利用すると相手が購入してくれやすくなります。
具体的には、「期間限定」「タイムセール」「今だけ」「限定●個」などの言葉を使い、相手を心理的に追い込むことで、購入してくれやすくなります。
まとめ
人間も動物なので、いろんな習性があるのは当然です。

そして、企業やお店などの販売者は、利益を出すためにあの手この手で自分のサービスや商品を売ろうとします。
その中には人間の習性を利用する場面もあります。
こういった学問を行動経済学というらしいですが、大手企業では、行動経済学の知識を持った人を雇い、その知識を使って、いろいろな商品やサービスを販売してきています。

逆に我々のような購入側でも、人間の習性をしっかり理解して、無駄な浪費をしないようにお金を守っていかなければなりませんね。
おまけ
このたび、我が家では、子供へのお金の教育について実践した模様を電子書籍(kindle版)にして出版しました!その書籍がこちらです!
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XVHJ5P7/ref=cm_sw_r_tw_dp_7RMX4CK1SNP1KRGC1ZFP
我が家で行った家庭内起業の模様をまとめたものです。お子さんのマネーリテラシーを向上させたい方は必見です。
また、実は、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、以下の部分をポチっとお願いします。筆者の励みになっています!
今回は、以上です。最後までお読みいただきありがとうございます。








コメント