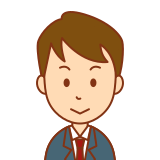
最近耳にする「円安」ってどういう意味?
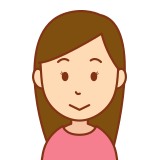
為替(かわせ)ってどうして毎日変化しているの?
こんなお考えをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ニュースなどでは、毎日、「1ドル=●円」などのように為替(かわせ)に関する情報が流れてきます。
為替は外国と日本の通貨を交換する際のレートです。
「我が家は外国に行く予定もないし関係ない」とお思いの方もおられるかもしれませんが、実は、私たちの生活にも大きく影響しています。
また、既に投資を始めている方で諸外国に関する金融商品をお持ちの方は、為替は損益に直結するので、動向は要チェックです。
この記事では、FPと簿記の資格を有する筆者が、以下の内容についてご紹介します。
日本の通貨(円)は、外国では使えません。
日本では、「円」という日本の通貨が使用されています。
同じようにアメリカでは「ドル」、中国なら「元」と、イギリスは「ポンド」など、その国の中だけで使うことができる、その国のお金があります。
国には、自国で流通する「通貨を発行する権限」があります。
そのため、例えば、日本のお金(円)をいっぱい持ってアメリカに行っても、そのままではそのお金を使うことができません。

そこで、外国で取引をしたい場合には、その国の通貨と両替する必要があります。
その時の、通貨間の両替のレート(値)が為替です。
円安(えんやす)・円高(えんだか)ってどういう状態?
ではよく耳にする「円高」や「円安」とは、どういう状態なんでしょうか。
レートは需要と供給で決まります。
円高=円の価値が高くなる、ということは、みんなが円を欲しがっているということです。
逆に、円安=円の価値が低くなる、ということは、みんなが、円を欲しがっていない状態。

例えば、1ドルに交換するのに、100円必要だったのに、ある時期、110円必要になった場合には、ドルに対して「10円円安」になったということになります。
また、逆に、1ドルに交換するのに、来月は90円必要になった場合には「円高になった」となります。
このように外国の通貨に交換する際に、多くの円が必要になる場合が「円安」、逆に少なくなる場合が「円高」です。
為替が変動する理由は?
為替は毎日というより毎秒変動しています。
為替は、その通貨の需要と供給で決まります。
簡単に言えば、「みんなが要ると思えば、価値が上がり、要らないと思えば、下がる」
では、具体的にどういった事情で為替(かわせ)が、大きく変化するのか、一例をご紹介します。
輸入や輸出をする場合
具体的には、日本の会社がアメリカから製品を輸入する場合、代金をドルで支払うには、手持ちの円を、まずドルに替える必要があります。
そのため、日本のお金(円)でアメリカで通用するお金(ドル)を買うという取引をします。

この場合、輸入する会社がたくさんあった場合には、みんながドルを欲しがるので、ドルに交換するためのお金(円)はたくさん必要になります。
また、逆に日本の製品をアメリカに輸出した場合には、代金をドルでもらうことになります。
日本の会社は社員の人たちに給料を支払ったりするときには、日本で使えるお金(円)で支払いますので、ドルは必要ではなくなり、かわって円が必要になります。
この場合、輸出する会社がたくさんある場合には、ドルはいらなくなるので、もしこの場面でドルに交換したいなと思った人がいた場合には、お金(円)はどれほど多くは必要ありません。
投資をする場合
例えば、日本の投資家がアメリカの株式や米ドルで発行された債券(国債や社債など)に投資をする場合には、「円を売って米ドルを買う」必要があります。
そういう投資家が増えれば、ドルの需要が高まり、ドル高・円安の方向に向かうでしょう。

一方で、アメリカの投資家が日本の株式や債券に投資を行う場合には、逆の流れが起こることになります。
一般的に投資家が投資をするのは、景気がいい国なので、そんな国で使えるお金は高くなることがあるようです。
物価の変動(インフレやデフレ)
また、物価(物の値段)の変動も、為替に影響を与える要因の一つです。
物の値段が上がっていき、インフレになる(世の中に出回るお金の量が増える)ということは、同時に、その国でのお金の価値が下がるということでもあります。

逆に、物価が下がっていく、つまりデフレ(世の中に出回るお金の量が減る)になると、お金の価値は上がっていきます。
仮に、アメリカでインフレが続き、日本でデフレが続けば、ドルの価値はどんどん下がり、円の価値が上がり、為替はドル安・円高に向かう可能性が大きくなります。
戦争や紛争がある場合
また、例えば、こんなことでも為替は変化します。

それは、戦争や紛争がある時などです。
戦争があると、場合によっては、国が潰れてしまうことがありますから、その国のお金を持っている人は、潰れそうにない国のお金を確保しておこうとします。
世界で戦争が起きると、ドルはアメリカという強大な国(潰れそうにない国)の通貨ですからニーズが高まります。そうするとドルの価値は高くなります。
経済指標などの発表による場合
経済指標(例えば、景気の具合)は世界経済に与える影響が大きく、為替も大きく変動することがあります。
例えば、アメリカの「雇用統計」。
雇用の状況が良ければ、失業率の低下や賃金の上昇を通して、アメリカ経済の拡大につながると予想されるため、統計の結果が予想を大きく上回ると、通常はドルが買われて円安になる傾向があります。
為替(かわせ)は、この他にもいろんな要素で変動することになるので必ずこうなる!と予想するのは、とても難しいと言われています。
「為替を予想できます!」という詐欺的な商品も出回っているのでご注意を!
為替の差を利用した金融商品(FX=外国為替証拠金取引)
為替は常に変動しています。
そこで、その変動に注目した金融商品があります。
それは、「FX(外国為替証拠金取引)」
例えば、「円高」のときにドルを買い、その後、「円安」になったときに売るとその差額が利益になります。
それを一定の証拠金を積んで、資金の何倍もの通貨を取引する(レバレッジ)金融商品です。
もちろん、ドルを買ったあとで、ドル安になってしまうと損失が出てしまいます。

為替は、いろんな要素で決まり値動きも複雑です。
そのため、予想するのは難しいので、FXは、為替差損が発生するリスクが非常に高い金融商品です。
「FXで確実に儲けられます」というような広告を売って、価値のない詐欺的商品を販売する業者にはご注意ください!
為替に影響されない新しい決済のカタチ(仮想通貨)
こうした為替は、国の事情によって変化してしまいますし、国同士のやりとりで調整することもできてしまいます。
国同士のやりとりがある以上、個人や会社が外国と何かをするときには、常に為替(かわせ)を意識しないといけません。

もし全世界が同じ通貨を使うことができれば、為替を気にすることなく、世界中の人がどこにいても自由にお金のやりとりができるようになります。
そこで、話題になっているのが、仮想通貨・暗号資産というものがあります。
国境のない通貨として注目されていて、例えば、日本で1ビットコインを持って、何かエジプトの人からモノを買う場合には、1ビットコインをエジプトの人に送金すれば足りて、為替を気にする必要がありません。

つまり、国の政策などに影響されないというメリットがあるとされています。
しかし、値段が安定しない、法規制がまだ確立していないなど、まだまだ詰めていかないといけない課題はたくさんありますが、将来「新しい決済のカタチ」になるかもしれません。
まとめ
この記事では、為替についてご紹介しました。
為替は、需要と供給で決まるもので、刻刻と変化しています。
そこでは、いろいろな事情に影響されます。
日常、外国と直接取引していない方も日常の生活では、輸入品に頼って生活していることが多いです。
そういう意味では、日本全員が為替について知っておく必要があるのではないかと思います。
今回の記事が参考になれば嬉しいです。
おまけ
このたび、我が家では、子供へのお金の教育について実践した模様を電子書籍(kindle版)にして出版しました!その書籍がこちらです!
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XVHJ5P7/ref=cm_sw_r_tw_dp_7RMX4CK1SNP1KRGC1ZFP
我が家で行った家庭内起業の模様をまとめたものです。お子さんのマネーリテラシーを向上させたい方は必見です。
また、実は、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、以下の部分をポチっとお願いします。筆者の励みになっています!
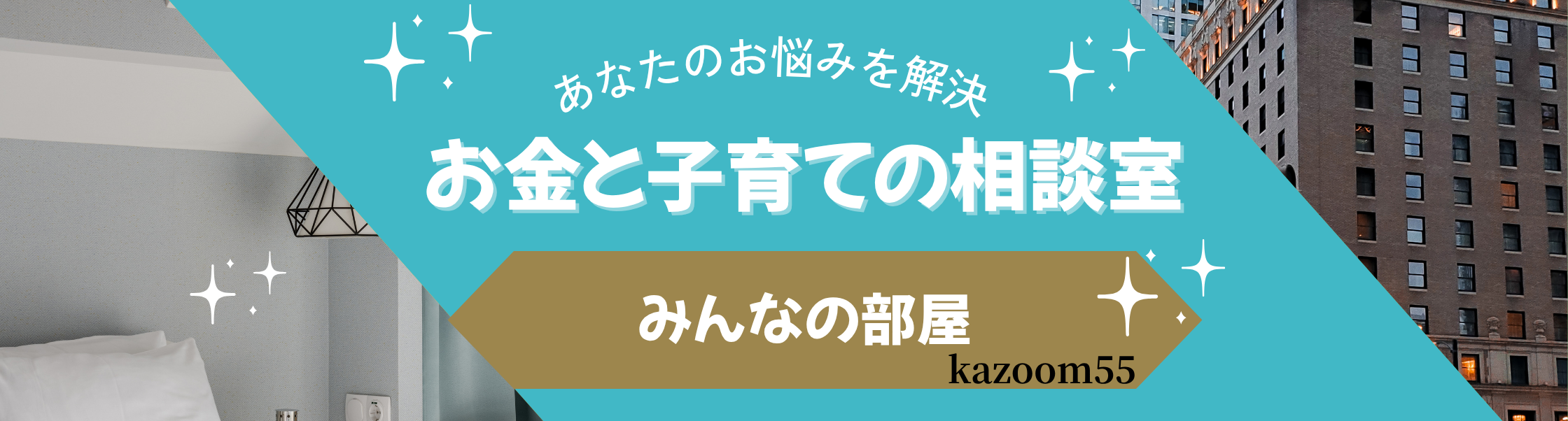




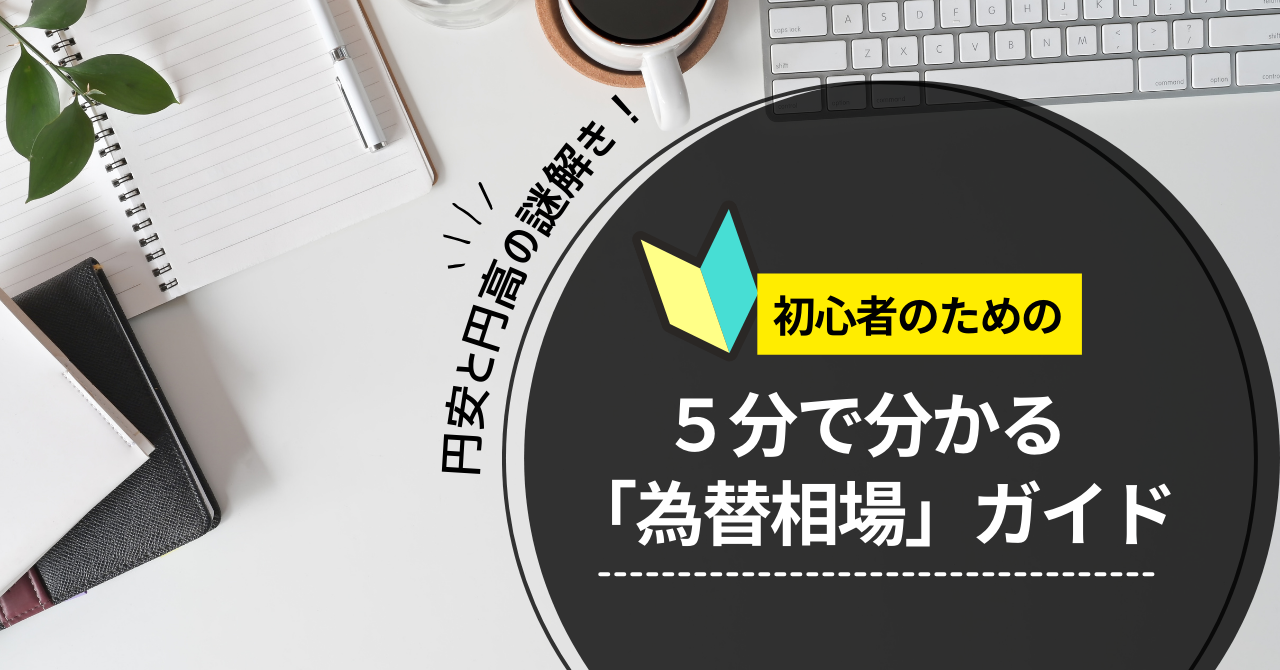


コメント