お正月といえば、なんといっても「お年玉」ですね。
「お年玉」は金額の大小や、誰からもらったかは、ご家庭によりますが、お子さんが1年に1回、大金を手にする時期なので、お子さんのテンションは上がります。
ただ、渡す側の大人としては。
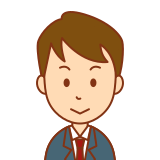
「お年玉」って、いつどれくらい渡せばいい?
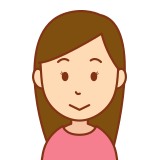
まとまったお金を子供に渡して大丈夫?
こんなお悩みの方お持ちの方も多いのではないでしょうか。
我が家にも3人子供がいます。
そこで、簿記とファイナンシャルプランナーの資格を保有する筆者が、以下の内容を解説します。
お子さんは「お年玉」でテンションが上がります。
テンションが上がっている時こそが、親子でお金のことを学ぶチャンス!
この記事をお読みの方のご家庭での参考にしていただき、親子でお金の勉強をするきっかけにしていただければ嬉しいです。
お年玉の由来は、「丸餅」だった!?
お年玉の由来はいくつか説があるようです。
最も有力とされているのは「お年玉」→「御歳魂」という説。
昔、お正月に歳神様にお供えした丸餅を、一家の主から家族や奉公人に分け与える風習があり、そうすることで、その一年は健康と豊作に恵まれると考えられていました。
丸餅には、「歳」神様の「魂」(たましい)が込められていて、それを分配していただくということから「おとしだま」となったというものです。
以後、時代とともに、丸餅をついて、歳神様へお供えする家庭が徐々に減っていき、昭和30年代からは、お金に変わっていったと考えられています。
また、アジア諸国にも由来はさまざまですが「お年玉」の習慣はあります。
しかし、欧米のようなキリスト教圏では、特にお正月を盛大に祝う習慣はないので、「お年玉」という習慣はありません。
【お年玉】の相場はいくら?→年代別にご紹介!
お年玉は、大家族から核家族(親と子の家庭)が増えるに連れて、渡す人数が減少したことから1人あたりの金額が増えたと言われています。
ある統計によれば、お年玉の平均額は長期にわたって上昇傾向にあり、1940年代からは約6倍になっているそうです。
「お年玉」の相場は、お子さんの年代によっても金額が違うのが特徴的です。
また、一般にお年玉は、ポチ袋に入れて渡すのが一般的です。
おすすめのちょっと変わったかわいいポチ袋はこちら。
【お年玉】の相場 未就学児は、500円から1000円
未就学児(小学校前)であれば、500~1,000円程度が相場です。
お年玉の金額というよりもプレゼントとしての意味合いが強いようです。
まだ、金額の大小という正確な理解がないことから低額なことが多いようです。
【お年玉】の相場 小学生3000円、中学生5000円、高校生1万円
小学生から高校生までは、12年間あるので、学年に応じて金額を上げていくご家庭が多いようです。
平均的な金額としては、次のとおりです。
学生になれば、お金の価値も分かり、自分で買い物ができます。
そこで幼少期よりも高額になってきます。
【お年玉】をやめるタイミング→高校卒業とともは終了!?
お年玉を止める時期については、決まっているものではありません。
高校卒業とともに自然とお年玉を止めているご家庭が多いようです。
これは、金額も大きくなり渡す側の経済的な負担が多いのと、お子さん自身がお金を手に入れることができる年代になっているからです。
もちろんご自身の経済状況や相手との関係を考慮することになります。
例えば、社会人になった時や成人した時などもお年玉を止める区切りとしては、いいかもしれません。
【お年玉】を使った「お金の勉強方法」→我が家の教育法をご紹介!
さて、貰う側の子供からすれば、1年のまとまった金額を受け取るのはお年玉の時期。
テンションも上がりますが、実は、大人にとっては、格好のお金の知識を身に着けることができる格好の時期なんです。
そこで、ここでは、「お年玉」を使った「お金の勉強方法」をご紹介します。
方法は簡単です。次の2つの質問をします。
【お年玉をもらうために何時間働く必要がる?】
例えば、お年玉の総額が2万円だった場合。
「そうすると、20時間!」という答えが返ってきます。
そこで、少しいじわるな質問をします。
ここで、税金の話をしたり、働く準備の時間などを取り上げて、「実際はもう少し働かないと手に入らないお金だよ」と説明します。
さらに。
そして、ここで、労働以外のお金の増やし方として「副業、起業、投資」などを説明します。
また、「1人では稼げる金額に限界があるから、より多くの収入を得ようとおもったらチーム(会社)が必要だよ」といって会社について説明します。
【お年玉を何に使うのが1番お得?】
お年玉の使い道は?→やっぱり貯金!(長女)
ある統計によると、お年玉の使い道第1位は、「貯金」です。ちなみに、毎年公開されるボーナスの使い道第1位も「貯金」です。
長女は「貯金!」と答えました。
そこで、子供たちに貯金のメリットを聞き出すと、「減ることはないから」「強盗などにとられることはないから」というような回答が返ってきました。
そこで、またまたいじわるな質問を。
というような問いかけをすると長女、全額貯金をすることが必ずしも最善の策ではないことに気づきました。
使い道は?→「ゲーム機の購入や課金!」(次男)
次男の回答は、「ゲーム機を買いたい!」
お小遣いの使い道で、貯金の次に多いのは、ゲーム機の購入や課金だそうです。子供にとっては(大人もですが)ゲームは、いつの時代も魅力的ですよね。そんなゲームにお金を使いたいというのは、自然かもしれません。
「おお!いいんじゃない!」といったあとに「値段」について質問しました。
「じゃ、このゲーム機は1年後、価値はどうなっているのかな」と伝えたところ、「今は買い時ではないな、もう少し待ってみよう」と納得した様子で、なにやら計画を立てていました。
使い道は?→「投資をする!」(長男)
長男からは、家庭内での金融教育の成果なのか「投資をして増やして買いたいものを買う!」という言葉がでました。
そこで、またまたいじわるな質問を。
と問いかけて、投資のリスクやハイリスクハイリターンの話をしたり、どういう事情があったら価額が上下するのかということを説明しました。
長男からは「全額は無理だなw」「○%貯金で○%投資したらどうなるだろ。」「今年はコロナの影響はどれだけ影響ができるのかな」というような声が聞こえました。
使い道は?→「自己投資をする!」(全員)
長女は全額貯金の方針を見直して「将来パンケーキ屋さんをしたいから本を買って勉強したい」と奇特なことを言っていました。
これに連なって長男や次男も本を買いたいと言い出しました。
そこで、「自分の将来に投資するのは素晴らしいし、一般の投資のようにマイナスになることはない。」ということを説明して「どんなジャンルに自己投資するか(どんな本が買いたいか)」という質問して考えさせた上で。
早速、3人は、どんな本を買うのか、真剣に調べていました。
アウトプットを想定したインプットをする必要があることや、自己投資は、リスクがない唯一の投資だということを伝えました。
まとめ
いかがでしたか。
お年玉をもらう場面というのは、お子さんがお金のことに興味を持っていてテンションが上がっている場面です。
テンションが上がった子供は無敵です。そして興味を持ったものについては吸収力も高い。
日ごろなかなかできないお金の話を、遠慮なく話せる場面なので、ご家庭で親子でお金の勉強を進める格好の材料になります。
是非、お子さんがお年玉を手に入れるタイミングで、親子でお金の稼ぎ方や使い方・税金などについて、ゆっくり話をしてみてください。
きっとお年玉以上のプレゼントになると思います。
おまけ
このたび、我が家では、電子書籍(kindle版)を出版しました!その書籍がこちらです!
勤労感謝の日に我が家で行った家庭内起業(ごっこ)の模様をまとめたシンプルなものになっていますので、参考にどうぞ♪
また、実は、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、ポチっとお願いします。すっごく励みになります♪
今回は、以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。
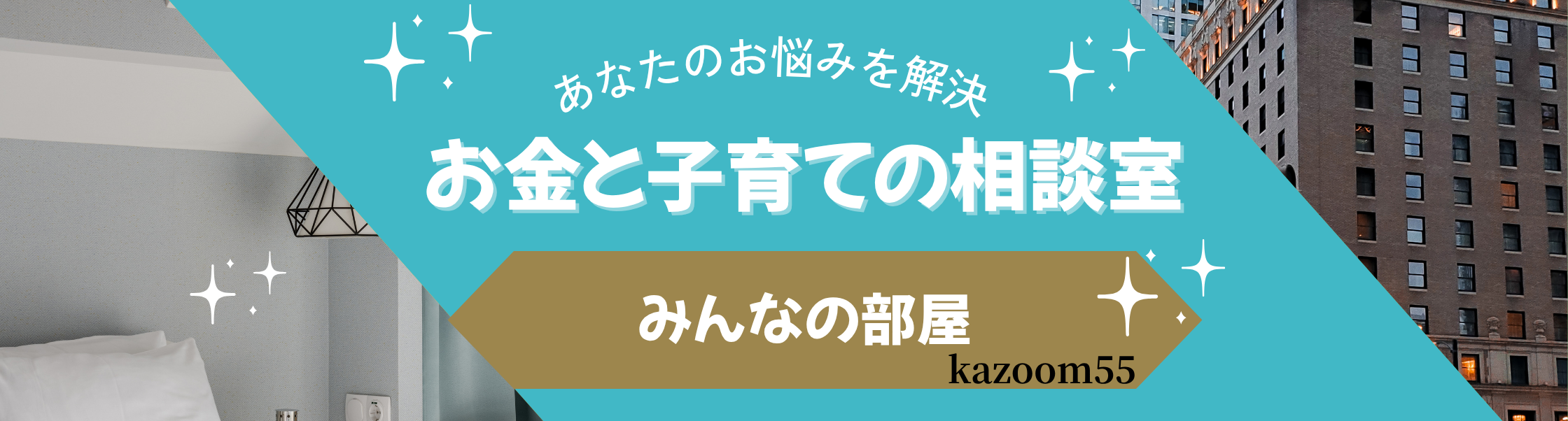




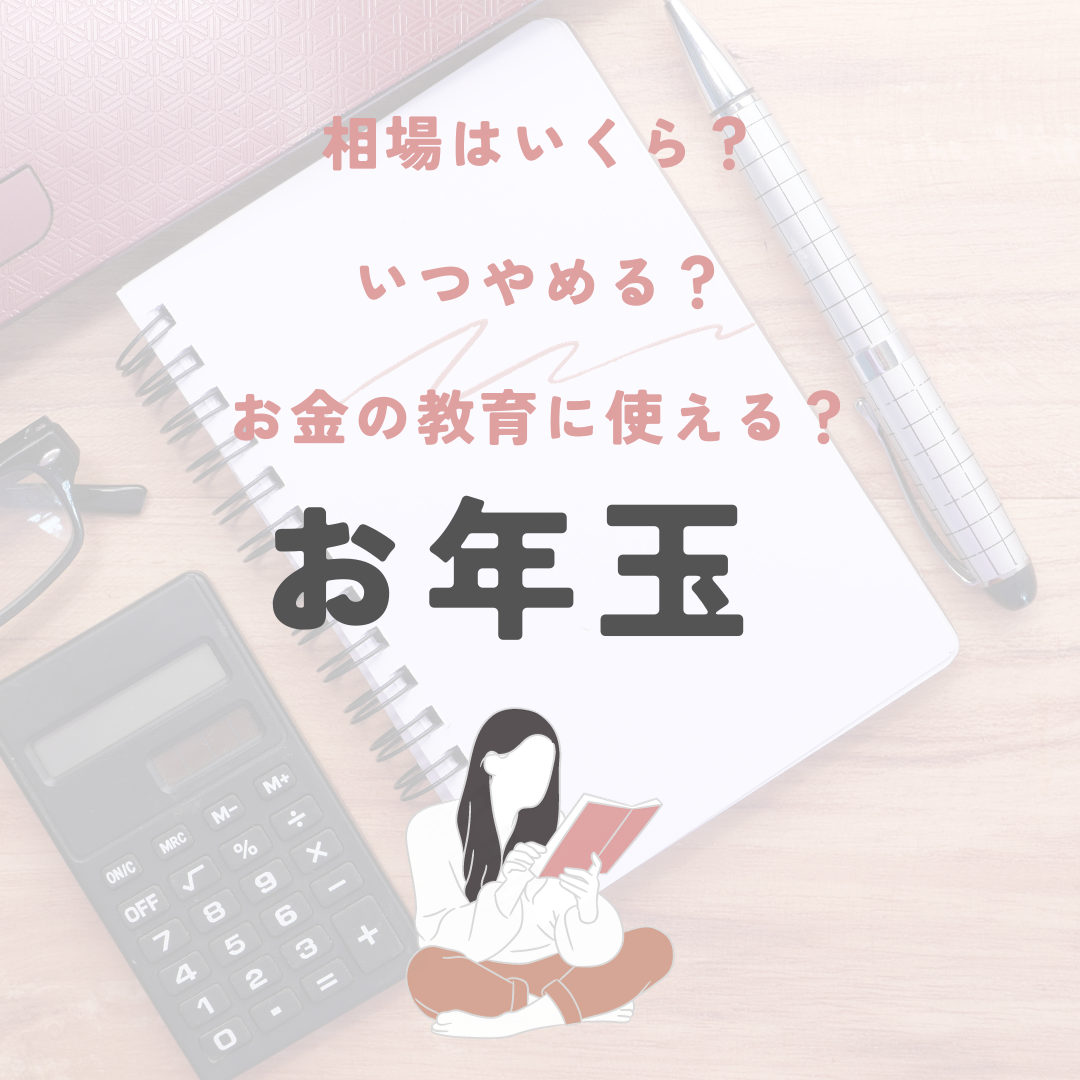


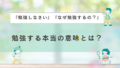
コメント