大学入学費用をなんとか抑えたい方へ
そんなふうに思っているご家庭も多いのではないでしょうか。
大学の進学費用は、「特別費」として家計管理の中でも最も頭を悩ませる存在です😅
我が家もまさにそうです。
3人の子どもを育てており、上の子は高校3年生。
来年はいよいよ受験というタイミングで、大学進学にかかる費用に不安を感じていました。
「借金はしないほうがいい」とは分かっていてもなかなか教育費を調達するのは難しい。
そんなときに大学の説明会で知ったのが、令和7年度から始まった「高等教育の修学支援新制度」の拡充です。
一般的なご家庭はもちろん、特に3人以上の子どもを扶養している世帯(多子世帯)には、大きな支援があるとわかり、本当に安心しました。
この記事では、我が家と同じように大学進学費用に不安を抱えるご家庭のために、この制度の概要と申請方法、注意点などを詳しくご紹介します。
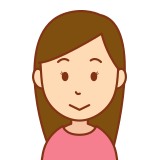
家計にきっと役立つと思うので最後まで読んでくださいね♫
「高等教育の修学支援新制度」ってどんな制度?
この制度は、経済的な理由で進学をためらう学生を支援するために国が行っている制度で、
① 授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)
② 給付型奨学金の支給(返還不要)

(※日本学生支援機構のパンフレットより抜粋)
令和7年度からは、多子世帯に対して収入要件なしで授業料・入学金の免除が受けられる特例が新たに導入され、対象の家庭には大きな助けとなります。
誰が対象になるの?
通常は「世帯収入が一定基準を下回ること」と「学ぶ意欲があること(成績ではなくレポート等で確認)」が条件です。
基本的には、進学を考えている高校生全員が該当することになります。
進学する本人が対象ですが、保護者の方も「自分の家庭が対象になるか」を事前に確認しておくことが大切です。
対象となる進学先にはどんなところがあるの?
支援の対象となるのは、国が認定した以下の学校です。
- 大学(国公私立問わず)
- 短期大学
- 高等専門学校(4・5年生)
- 専門学校
全国の多くの学校が対象になっています。
どれくらい支援してもらえるの?
自宅通学か自宅外通学か、学校の種類(大学・短大・専門学校など)によって金額が異なります。
この制度の支援方法は「授業料・入学金の減免」と「給付奨学金の支給」ですので、以下では分けてご紹介します。
授業料・入学金の減免
・授業料・入学金の減免については、以下のとおりです(返還不要)。

(※日本学生支援機構のパンフレットより抜粋)
給付型奨学金
給付型奨学金の場合には、本人の生活費の負担軽減のため、返還不要の奨学金を支給されます。
こちらは、対象者を扶養している方の収入に応じて変わります。また、自宅から通うのか、自宅外かで金額も変わります。以下は年額です。

(※日本学生支援機構のパンフレットより抜粋)
また、授業料等の減免との併用は可能となり、実質「無償で進学」することも可能となります。
【モデルケース1】私立大学に自宅外から通う場合(最大額)
給付型奨学金:約91万円/年
授業料の減免:上限 約70万円/年
入学金の減免:上限 約26万円
→ 合計で最大 約187万円/年の支援
【モデルケース2】私立専門学校に自宅から通う場合(最大額)
給付型奨学金:約46万円/年
授業料の減免:上限 約59万円/年
入学金の減免:上限 約16万円
→ 合計で最大 約121万円/年の支援
※住民税非課税世帯に準ずる世帯は、この支援額の2/3または1/3が支給されます。
支援を受ける手続き方法
ここでは、支援を受ける手続きをご紹介します。
高校在学生の申請手順をご紹介しますが、既に大学等の進学している方も対象となりますので、そのような方は通学先にお問い合わせください。

(※日本学生支援機構のパンフレットより抜粋)
「進学資金シミュレーター」を使って事前確認!
「自分の家庭が支援対象かどうか確認したい」という方は、JASSO(日本学生支援機構)の「進学資金シミュレーター」を活用することをおすすめします。
▶︎ 進学資金シミュレーター
収入や家族構成を入力するだけで、支援の対象になりそうかを簡易的に判定できるので、便利です♪
ただ、あくまで試算ですので、実際の支給額と一致するとは限りませんのであくまで目安としてご利用ください。
制度を使う上での注意はあるの?
この制度を利用するのにはいくつか注意点があります。
ここでは主な注意点をご紹介します。
支援を受けるには、在学中に「学業要件」を満たす必要
→ 定期的な出席、学修状況の報告、成績の一定基準維持が求められます。
→ 達成できない場合は支援が打ち切られることもあります。
授業料減免は入学後3か月以内の手続きが必要
→ 申請が遅れると入学金の減免対象にならない可能性も!
高校で予約採用が不採用の場合でも進学後に再申請可能
→在学採用の申請枠で進学後も申し込めます。
以前の奨学金制度を使っていても切り替えは可能
→ 令和元年度以前の給付型奨学金から新制度に切り替え可能です。
まとめ|今から準備できること
この記事では、大学進学費用に悩む世帯を支援する「高等教育の修学支援新制度」の概略をご紹介しました。
いろいろな条件はありますが、返済不要の国の奨学金制度になるので「借金」をしなくても教育費の一部を調達することが可能となります。
さらに、令和7年度からは、3人以上の子を扶養する世帯なら収入制限なしで授業料・入学金の減免が受けられ、さらに、収入によっては返済不要の給付型奨学金も支給されます。
条件を満たせば、実質「無償進学」も可能です。
手続きは早めに行い、進学資金シミュレーターで対象かどうかをチェックしましょう。
お子さんの未来のために、ぜひこの制度の活用を検討してみてください。
参考リンク(公式情報)
文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/
日本学生支援機構(JASSO)進学資金シミュレーター
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html
日本学生支援機構 奨学金公式サイト
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html
筆者活動のご紹介
ここでは、筆者の活動をご紹介します。お力になれるものがありましたらお問い合わせフォームからご連絡ください。
ランキングに参加
現在、「にほんぶろぐ村」のランキングに参加中です。今回の記事に共感していただけましたら、以下の部分をポチっと押していただけますと、筆者の励みになります!
✨✨✨【金融・金銭教育部門】第1位✨✨✨
ウェブライターのお仕事の受注
筆者はウェブライターとしても活動させていただいております。もしお役に立てることがありましたら、お問い合わせフォームからご連絡いただけますと幸いです。
▼執筆経験のある主なジャンル
・金融系(お金の知識など)
・不動産系
・学習系(特に金融・法律)
・資格
・学校の紹介
・子供の教育
電子書籍(kindle)の出版
このたび、我が家では、親子で挑戦した記録を電子書籍(kindle版)にして出版しています!
その書籍の一部をご紹介します!出版のご相談も承っていますのでご連絡ください。
「やってみな、わからん」M-1グランプリ1回戦突破の小学生兄妹コンビの挑戦記
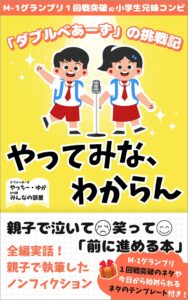
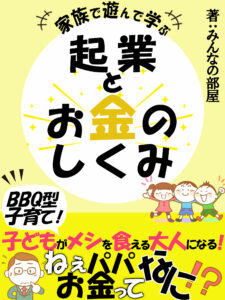
最後までご覧いただきありがとうございました。
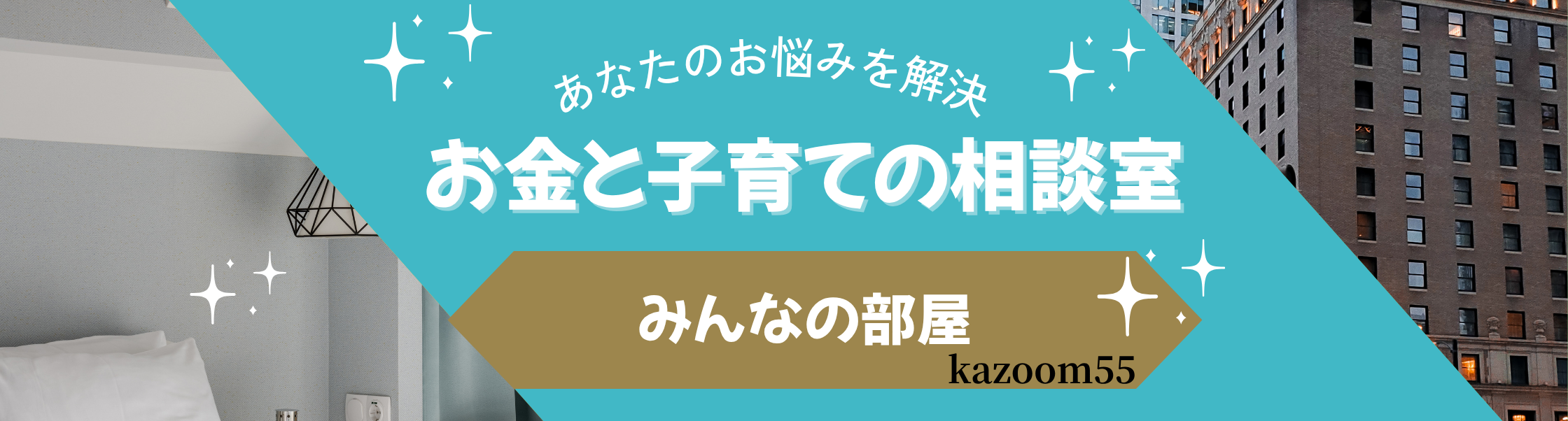




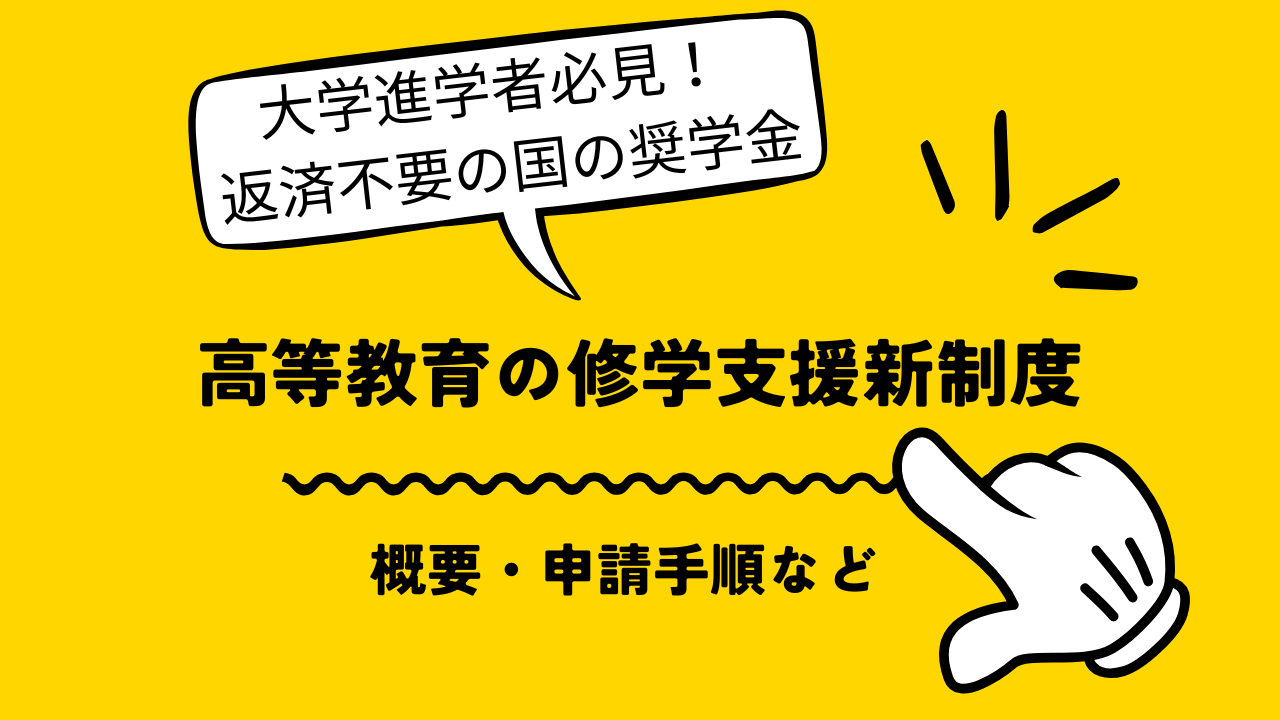


コメント