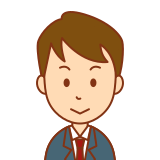
魅力的な大人になりたいけど、どうしたらいい?
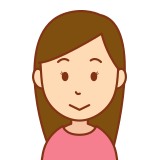
みんなに好かれている人の共通点は?
こんな思いを持ったことのある人も多いのではないでしょうか。
自己啓発本などには、よく「失敗を恐れず挑戦しろ!」という趣旨の言葉が書かれていたり、インフルエンサーが動画の中でも同様の発言などがあります。
その時は、テンションがあがります。
でも、しばらくすると、結局のところ、何も行動しない。
原因は・・・
「魅力的な大人になりたい」けど「失敗したくないから挑戦はしない」というマインド。
そこで、この記事では、コンビニで陳列されている「あの商品」を例に挙げ「魅力的な大人のなり方」と「失敗の捉え方」について、ご紹介します。
コンビニにある「役に立つもの」と「意味があるもの」
ところで、世の中のモノやサービスは、次の2つに分かれます。
- 役に立つもの
- 意味があるもの
例えば、コンビニで売っているハサミやホッチキスなどの文房具は、紙を切ったり、貼り付けたりするときに便利です。
つまり、切れ味や機能を重視されて「役に立つもの」として販売されています。

一方で、カウンターの奥に陳列されているのは「タバコ」
タバコは、文房具のように便利ではありません。
場合によっては、健康を害する可能性すらあるものです。

では、どうしてタバコを買うのか?
筆者は昔、タバコを購入していましたが、タバコを購入する際は、「ガツンとくるタバコが好きだ」とか「僕は当時のドラマの主人公が吸っていたこのタバコが好きだ」などというように「何か背景事情」がある場合が多いものです。
つまり、買う側にとって便利ではなりませんが、タバコは買う人には、何かしらの背景事情、つまり「意味があるもの」として販売されています。
コンビニの「文房具」と「タバコ」の陳列数が違うの?
では、品数はどうでしょうか?
コンビニやスーパーで陳列されている文房具は、せいぜい多くても2~3種類。
それに比べると、レジの奥には、たくさんの種類のタバコが陳列されています。
この陳列数の違いはどこにあるのでしょうか?
文房具の場合には、切れる機能や接着できる機能があればよく、「役に立つものは1つだけ陳列していればでいい」
2番目に切れ味の鋭いハサミとか、2番目に留められるホッチキスなど要りません。
しかし、タバコはどうでしょうか?
1番ニコチンの多いものだけおいていても、1番カラフルなデザインのタバコだけ置いていてもお客さんは満足しません。
それぞれのタバコに意味(背景事情)を持って購入するお客さんのために、いろんな種類のタバコが置く必要があります。
「魅力的な大人とは?」・・・「役に立つ人」ではない
では、人間に置き換えてみたらどうでしょう?
「役に立つ人間」と「意味のある人間」
役に立つ人間
「役に立つ人」というと特殊能力と呼ばれるスキルを持っている人たちです。
これまでは、能力は素晴らしいものとして重宝されてきました。
しかし、例えば、これまで計算の速さをウリにしてた人は電卓が生まれた瞬間に一気に必要とされなくなりました。
知識をウリにしていた人はGoogle ができた瞬間に一気に必要とされなくなりました。
そこそこおいしいラーメンは誰も作れるようになりましたし、AIを使ってプロ並みの文章や絵を描くことができます。
「役に立つ人」(機能が優れている人)は、今後も価値が薄れていきます。
さらに、文房具と同じように「役に立つ人」は1人で良い。
そして「1番役に立つ人」になるのは至難の業です。
例えば、電卓よりも早く計算する人は見たことがありませんしgoogle よりも、物知りの人になるのは難しいかもしれません。
そういった存在になり人々未了するにはかなり難しいようです。。。
意味のある人間
「意味のある人」とは、面白そうな背景事情を持った人である人です。
決して優れているわけではないんだけども何となく興味をそそる人とも言えます。
筆者の友人にも・・・
- 決して出世していたり地位がある訳ではないけど話の内容がとても面白い人
- 決してルックスが抜群に良いとはいえないけど、みんなから愛されている人
- 理由は分からないけど、いつも周りに人が集まってくる人
友人たちに共有するポイントがあります。
それは、「ストーリー(物語性)」
友人たちは、これまで生死を分けるような闘病の経験をしてきたり、会社経営に大失敗をしてきたり、解雇処分の一歩手前だったり、夜逃げ経験があったり・・・
決して順風満帆ではなく、苦労や努力、歯を食いしばった頑張りが背景事情としてあります。

昔、見たヒーローもののアニメも必ず1回は最大のピンチを経験しています。
悪戦苦闘ぶりが観ている側に「応援シロ」を作ります。
浮き沈みのあるストーリーが非常に重要で、そのためには、沈む時間=失敗も必要かもしれません。
その失敗と成功のギャップに人々は魅了されるのかもしれません。
まとめ
魅力的な人というのは、タバコのようにストーリーを持っている人です。
では、そうやってストーリーはどのように作って魅力的な人になるのか。
答えは、シンプルです。
挑戦して失敗することです。
失敗はしないけども何のストーリーも生まれない、その代わり、より過酷な機能勝負の戦いに挑まないといけない道を選択をするのか、失敗はするけどもストーリーが生まれて、意味を武器に戦いに挑むのか。
この記事を読んでいただいた方は、どちらが魅力的な大人かお分かりいただけたのではないかと思います。
参考にした書籍は、以下のとおりです。よろしければ、タップ(クリック)してご覧ください。
書籍(楽天):プロセスエコノミー あなたの物語が価値になる [ 尾原和啓 ]
書籍(アマゾン)プロセスエコノミー あなたの物語が価値になる (幻冬舎単行本)
おまけ
このたび、我が家では、子供へのお金の教育について実践した模様を電子書籍(kindle版)にして出版しました!その書籍がこちらです!
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XVHJ5P7/ref=cm_sw_r_tw_dp_7RMX4CK1SNP1KRGC1ZFP
我が家で行った家庭内起業の模様をまとめたものです。お子さんのマネーリテラシーを向上させたい方は必見です。
また、実は、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、以下の部分をポチっとお願いします。筆者の励みになっています!
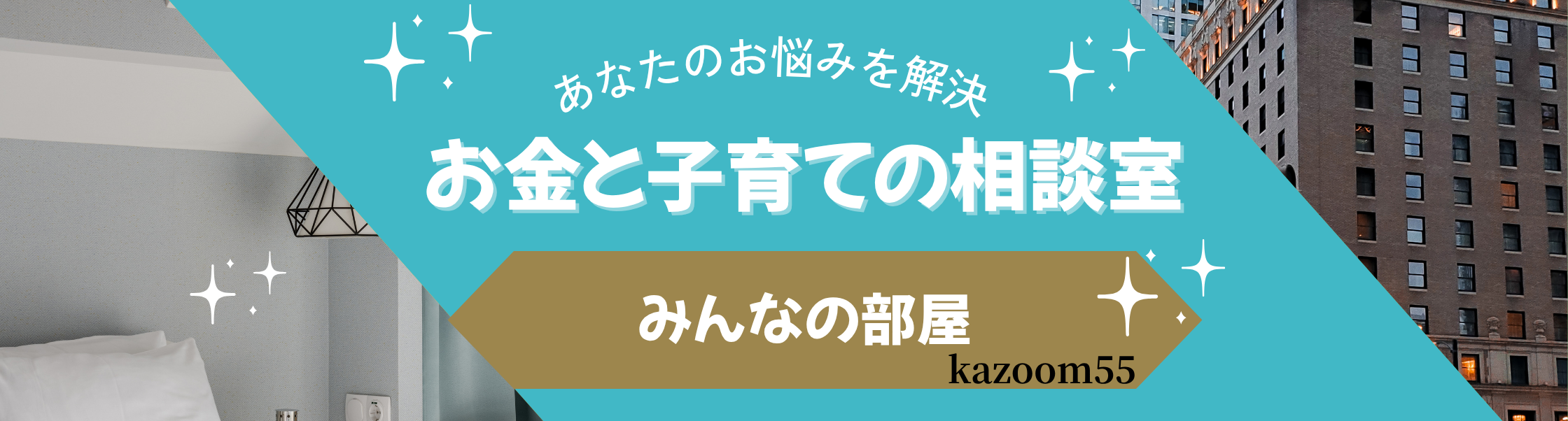





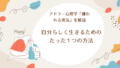

コメント