ご挨拶
どうも、かず~むです。私は文系の平凡なサラリーマンです。
よく仮想通貨が値上がり値下がりだけが取りだたされていますが、実は、この背景には、ブロックチェーンという技術(仕組み)があることをつい最近知りました。(→遅い!)
この記事を読めば、「ブロックチェーンのイメージ」が分かるかも!
「ブロックチェーン・・・なんだそれ、ビットコインのこと?」と先日まで思っていました。
ところが、このブロックチェーンという奴、実はすごい奴かもしれないんです。
どれくらいすごいかというと、もしかしたら世界をガラッと変えるかもしれない可能性があるらしいです。

また、最近では、ブロックチェーンを利用した新たな試み(NFT)なんかもどんどん登場していますので、その理解にも繋がるかもしれません(NFTに関する記事は以下からどうぞ)

そこで、今回は、このブログでは「ブロックチェーン」の紹介に挑みたいと思います。
とはいえ、なにぶん平凡な文系サラリーマンですので、細かい説明や専門的な説明は、他のサイトや専門家に任せるとして、素人なりに概略を分かりやすく紹介できるように頑張りますので、みなさんの参考にしていただければ嬉しいです。
それでは、ご紹介します。
ブロックチェーンとは?
一言でいうと、「仕組み」です。ブロックチェーンは、目に見えるものではありませんし触れるものではありません。
どんな仕組みかというと、「ブロックチェーンの参加者全員に、同じデータを分散・保管させて、、不正をする人や正常に動作しない者がいたとしても、正しい取引やデータのやりとりが維持でき、改ざんが非常に困難で、動作も停止しないようにする仕組み」です。

つまり、みんなで同じデータを持っていて、相互に確認できるから1人が書き換えても「おい、ちょっと待てよ!それ、改ざんしただろ!」と言えるし「あれ、なんだか故障したみたいだぞ」となっても他の人の持っているデータを利用してやりとりできるので中断されないということです。
どうして「ブロックチェーン」という仕組みが生まれたの?
では、どうして「ブロックチェーン」は誕生したのでしょうか。それは、最近よくCMや広告などで「5G(第5世代移動通信システム)」が関係していると言われています。
5Gの誕生。

この5Gってどういう意味なんでしょうか。1Gから4Gまでは何だったのでしょうか?
5Gというのは通信の技術の段階を表していて、具体的には、
- 1G ワイヤレスで音声通話が可能
- 2G テキストメッセージが可能
- 3G 携帯でインターネットが可能
- 4G 通信速度が向上しビデオ会議やゲームが可能
- 5G 高速・大容量の通信が可能になり、多数の機器と同時に接続できるようになる

と、いうような流れになっているそうです。今はスマホ以外にもいろんな機器がネットワークで繋がろうとしている時代だそうです。
そして、その世代交代の過程では、はじめは珍しく革新的であったものも徐々に日用品化していって当たり前のものになっていく現象も生じています(コモディティ化)。
たしかにあんなに珍しかったスマホは、今では誰でも持っているようになっています(→美男美女は3日で飽きるということと同じ?)。

また、インターネット上の取引も変化していきました。
インターネットはもともと企業同士のものから、スタートしました。だから昔は、オフィスオートメーション(OA)などと呼んでいて、パソコンもワープロも会社のためのもので会社に売っていた時代がありました。
それが、だんだん企業からお客さんに売るようにになって、メルカリのように個人間で取引をする道具になってきました。
その後SNSが発展し個人で発信できるようになり、またそれを多数の人に公開できるようになりました。
と、いうことで、一言でいうならば、「大容量の通信で何にでも誰にでも繋がっている状態」になったということです。
5G時代の4種の神器
そんな5G時代には4つの大きな技術があります。どれも最近どこかで聞いたことのある言葉かと思います。
IoT (データを集める作業)
インターネットにすべてのものがつながっている状態のことで、スマホやのような機械だけではなくて、靴や眼鏡や冷蔵庫やテレビや洗濯機・・・など日用品などもすべてインターネットに繋がっている状態です。スマホ1つで、いろんなものが動かせるような状態です。

クラウド(データを保存する作業)
従来は手元のコンピュータに導入して利用していたようなソフトウェアやデータをインターネット上からダウンロードして使用できたり、パソコンの中に保存していたデータをインターネット上に保存したりできる技術のことで、パソコンが変わってもそこからデータをダウンロードすれば効率的に引き継ぐことができる、いわばインターネット上のデータの保管庫です。

AI(データを活用する作業)
人工知能が人間の脳のような機能をもってデータを使っていく技術です。集めたデータを人間をはるかに超えるスピードで分析して最適解を出すことができる技術です。

ここで、「ブロックチェーン」
そして、4つ目の神器がブロックチェーンです。ブロックチェーンは、データを正確かつ安定的に管理します。いろんなものと繋がれるようになったので、それぞれ繋いだうえで相互に監視させてデータを正確に管理できるという仕組みです。
4種の神器は関連している!?
そして、この4つ(IoT,クラウド、AI,ブロックチェーン)は相互に関連していると言われています。
具体的には、IoTで大量のデータを集めて、クラウドに大量のデータを保存して、ブロックチェーンで管理して、AIでそのデータをどう活用するか考え実際に活用する、これが5G時代以降の世界だと言われています。
このように、集めたり保存したり活用しているデータを、どのように管理していくのがいいのか、そんな中で生まれたのがブロックチェーンという仕組みです。
ブロックチェーンの特徴は?
そんなブロックチェーンの特徴は次のようなものです。引っ越しを例に挙げると分かりやすいかもしれません。

①集めて並べる(暗号化技術)
ブロックチェーン内の通信は、途中で見られないように全部暗号化されています。
例えば、引っ越しの際に、食器や、本などを梱包し、どんなお皿が何枚入っているかが外から見て分からないように箱をに詰めますよね。
ブロックチェーンの仕組みも情報を梱包して外から見えなくして、箱に詰めていくそれが一定量たまったら、別の箱(次の番号をふった箱)に詰めて封をして、箱が外から見える状態で順番に並べられる。
その箱の並びは(番号をふるイメージで)外から確認できるようにしておく、ブロック状のものをチェーン状にならべるからブロックチェーンということです。

②みんなで確認(コンセンサスアルゴリズム)
①の内容をみんなで確認することもブロックチェーンの特徴です。
例えば、ダンボールに詰め込む際に、コップやお皿を入れているところをみんなで確認することになります。その箱に何が入っているかをみんなで確認するという特徴があります。
③みんなで持つ(DLT(分散型記録台帳)
そして、②の記録はだれか1人で持つのではなくてみんなで持つ。
みんなで同じものを持っているので、こそっと中身を入れ替えようとしても「これ、誰かが入れ替えただろ」とすぐに分かることになります。
違うデータが出た場合、まわりとチェックすれば、すぐにばれてしまうということです。
④リーダーはいない(P2P)
みんなで管理するので、リーダーはいません。
誰かが管理しているわけではない(みんなで管理している)ので、仕組みができたら、ずっとその状態で管理することができることになります。

例えば、これまで、特定の誰か(少数または1人)が管理することで、かかっていた設備投資やコストは不要ですし、ブロックチェーン会社みたいなものも要りません。
そして、どこかに支障が生じても複数で管理しているので、データが丸ごと無くなった!みたいなことは生じないと言われています。
これらの特徴の結果、データを正確に管理することができるようになる仕組みです。
ブロックチェーンで何ができる?
ブロックチェーンができることを一言でいうならば、「正確なデータ(記録)を残すこと」です。
そして、この「正確なデータ(記録)を残すこと」ということができれば、不動産取引、証券取引、保険契約、送金になどの金融に関する取引やシェアリングサービス、著作権管理、美術品の所有権、医療サービスなどの分野や行政手続や投票まで、公正で透明性が求められる分野に幅広く活用できることになります。

そして、これを通貨で利用できないかということで生まれたのが、ビットコインを初めとする暗号資産(仮想通貨)ということになります。
私は、ここで、ブロックチェーン=仮想通貨ではないことがようやく分かりました。(遅い!)
例えば、最近よく報道されている文書の改ざんなどについても、一度正しくブロックチェーンに記録してしまえば、書き換えのない適正な記録として残すことができるので、改ざんはできなくなり不正がなくなります(なんせみんなで確認しているのですぐバレる)。
管理者を必要としないため(みんなで同じものをもっているため)、個人情報が管理のために、どこかに集められることもないし、改ざんが困難なため見知らぬ個人間の取引であっても、安心して行えることになります。
ブロックチェーンのデメリットと課題
そんなブロックチェーンも万能な仕組みではなくデメリットやまだまだ課題もあります。
デメリットは次のとおりです。
- データを消せない、隠せない
- 時間がかかる
メリットと矛盾するようですが、一度記録した個人情報は二度と削除できなくなってしまうだけでなく、ネットワーク上の全ての参加者に情報が行き渡ってしまう。「こそっとあなただけに」ということができなくなってしまうので、これがデメリットになってしまう場合があるので、工夫が必要になると言われています。
また、新たなデータについての認証までに時間がかかることも挙げられます。
例えばカード決済をしようとした場合、新たな情報をネットワーク参加者に情報を行き渡らせてみんなで確認してOKと承認してもらって、初めて決済完了ということになります。
そして、その取引データが巨大化した場合には、かなりの通信量や管理するデータ量が増えるため、処理には相当の時間がかかってしまうと言われています。
速度が求められる分野においては、大きなデメリットともなるかもしれないので、処理する側の性能を上げるなどの工夫が必要かもしれません。
そして、現在では、次のような課題も挙げられています。
- 法律
- 既得権
- 理解の遅れ
国は中央集権的に管理しているため、なかなかこの技術を認めません(法律)。また、独占が許されない仕組みであるため、今ある大企業(銀行や大手の会社)は嫌がります(既得権)。そして、技術が難しくて、できることとできないことを理解できる人が少なく、「1人がやろう」と言ってもあんまり意味がありません。
このようなに、まだまだブロックチェーンには課題があるのも事実です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は、素人なりに「ブロックチェーン」について、ざっくりまとめてみました。
ブロックチェーンには課題もありますが、魅力的な仕組みです。
ところで、ブロックチェーンは、自律分散型と言われて、「みんなで同じデータを持ってみんなで確認することで、壊れにくく正確なデータを管理しようという仕組み」です。
一方で、その対になるのは、独占であったり、中央集権です。
今、インターネットを使った各種取引の実権を握っているのボスは、あの企業たちです。

でも、今その企業に対する不平等感、その企業を使わないと生きていかないのといけないのかと疑問を持つ人が多くなってきています。
そのときに、他の神器と比較してもブロックチェーンだけが、リーダーを作らない構造になっています。
ということは、(課題は大きいですが)この仕組みが広がれば、ボスを倒す唯一の方法ともいえるかもしれません。
そういう意味では、ブロックチェーンには未来を変える可能性があるかもしれませんね。
今回は、以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。
今回参考にした書籍はこちらです。もう少し深堀りしたい方は、ご購入を検討してください





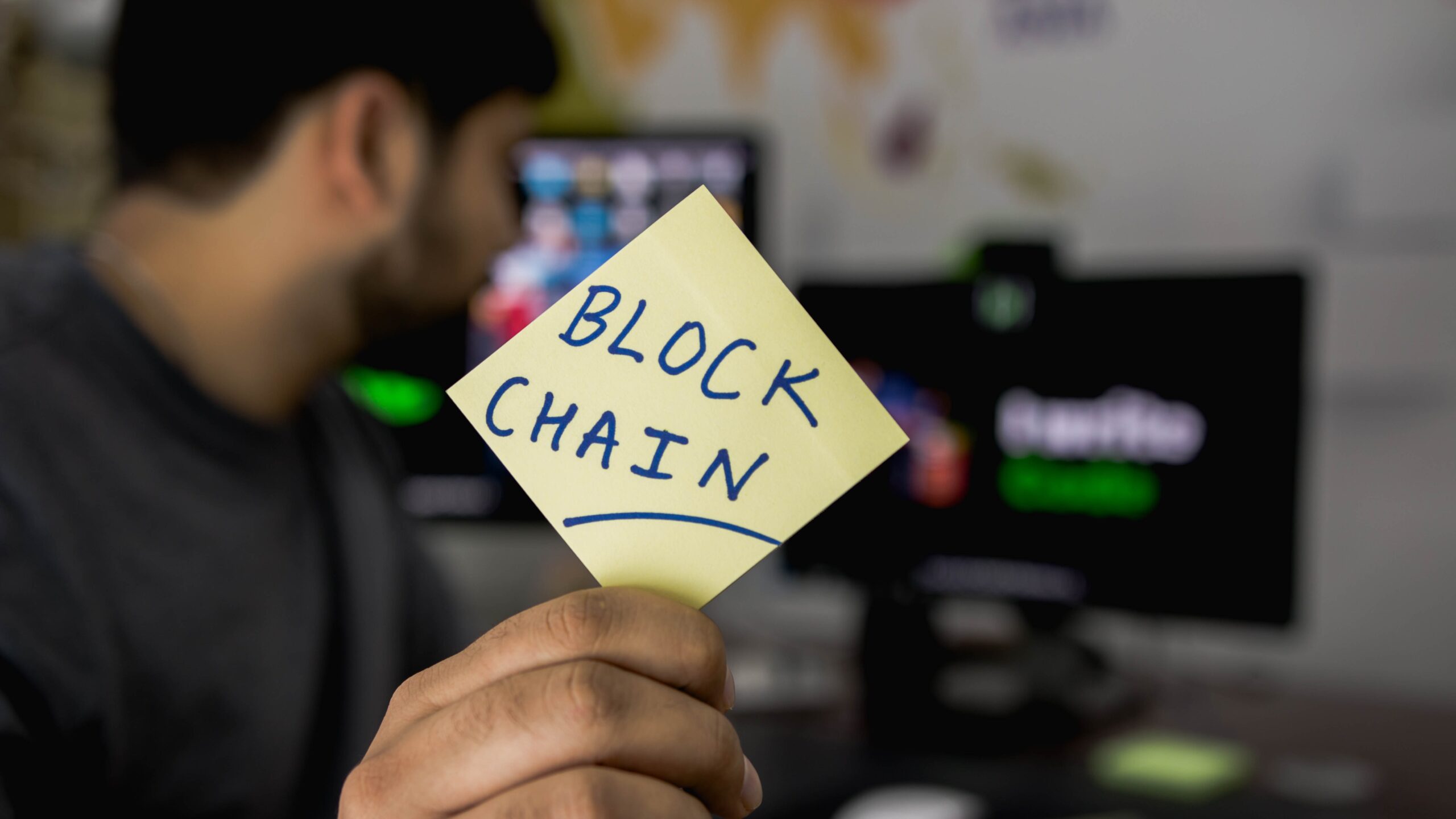


コメント