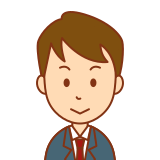
「ふるさと納税」ってなんかめんどくさそう!
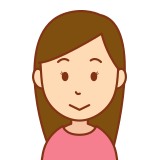
「ふるさと納税」をするとどんなメリットがあるの?
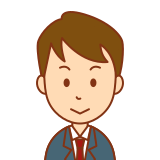
自分の出身地にしかできないんじゃないの?
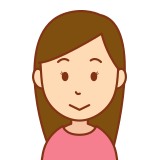
返礼品について詳しく知りたい!
こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税の利用率は、約15%。。。
「ふるさと納税」のメリットやデメリットが分からないので、なんだかめんどくさそうと思っている方も多いようです。
「ふるさと納税」とは、「納税」という言葉が使われていますが自治体に対する「寄付」です。
手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
筆者は、5年前からふるさと納税をしており、数々の返礼品などをいただき、家計に役立てています。
この記事では、「ふるさと納税に興味があるけど、やったことがない人」や「ふるさと納税をあまり知らない人」のために、ふるさと納税のメリット・デメリットをご紹介します。
この記事で使用している画像をタップすると各返礼品の詳細を見ることができます。
「ふるさと納税」のメリット
そもそも筆者が「ふるさと納税」をおすすめする理由は、たくさんのメリットがあるからです。
具体的には、以下のメリットがあります。
「ふるさと納税」のメリット① お礼の品(返礼品)がもらえる
「ふるさと納税」の最大の魅力は返礼品がもらえること!
多くの自治体では寄付への感謝として、地域の名産品などを「返礼品」にして寄付者に届けています。
自治体にとっては、「返礼品」を通じて、地域の名産品や産業を全国の人に知ってもらえる貴重な機会にもなっているのです。
まさにWINWIN(ウインウイン)の関係です。
「ふるさと納税」のメリット② 好きな自治体を選べる
ふるさと納税は、自分の生まれた場所や住んでいる場所の自治体に限られません。
例えば、沖縄出身の人が、北海道の自治体に寄付してもいいし、関西在住の人が関東の自治体に寄付してもOK
最近では、自然災害等で被災した自治体に寄付している人も多いようです。
応援したい自治体や返礼品が魅力的な自治体を選ぶ人が多いようです。
「ふるさと納税」のメリット③ 使い道が選べる自治体もある
ふるさと納税では、まちづくりや復興支援、子育て支援など寄付金の使い道を指定できる自治体が多くあります。
もちろんお任せという選択肢もOK。
自分の寄付を使い道を決めることができるメリットがあります。
筆者は、その自治体のHPなどを見ながら、その自治体が1番力を入れていそうな使い道を指定することが多いです。
「ふるさと納税」のメリット④ 税金の控除(還元)が受けられる
「ふるさと納税」は、「納税」という言葉が含まれていますが、実態は、「寄付」です。
ふるさと納税では、控除上限額内で寄付を行うと、合計寄付額から2,000円を引いた額について、所得税の還付、住民税の控除(減額)を受けることができます。
控除上限額は収入や家族構成によって異なりますが、例えば、4万円ふるさと納税をした場合には次年度以降、3万8000円分の減額を受けられることになります。
このため、実質2000円の負担で返礼品を獲得することができます。
「ふるさと納税」のメリット⑤ ポイントが付与される
ふるさと納税はクレジットカードの利用が可能です。
クレジットカードを利用すれば、使用額に応じてポイントが付与されますし、ポータルサイト内でポイントが付与される場合もあります。
寄付金額が大きくなるので、ポイントもしっかりゲットしておくと、実質の負担額はさらに軽減されます。
「ふるさと納税」のメリット⑥ 5自治体までなら確定申告不要
通常の寄付をして、税金を控除をしてもらう必要がある場合には、「確定申告」が必要です。
この点、「ふるさと納税」では、5自治体以内であれば「ワンストップ特例制度」というのを利用することができ、確定申告が不要。
逆に、年間の納税先が6自治体以上になると、給与所得のみの人でも確定申告が必要になります。
「ふるさと納税」のデメリット
このようなメリットの多い「ふるさと納税」ですが、イマイチ利用が進まないのは、なぜでしょうか。
それは、以下のようなデメリットがあるからです。
「ふるさと納税」のデメリット① 先に出費しないといけない
ふるさと納税の実態は寄附なので、先に出費をしなければなりません。
金額に応じて翌年の住民税や所得税から控除される仕組みなので、出費が先になります。
手元のお金にそれほど余裕がない場合に、無理に寄附をしようとすると負担になってしまいます。
最終的に2000円を引いた分が控除により戻ってきますが、戻ってくるタイミングは翌年です。
このように先に出費しないといけない、翌年にならないとメリットを感じられないというのが、「ふるさと納税」が流行らない大きな要因です。
「ふるさと納税」のデメリット② 減税・節税効果なし(税金前払い)
「納税」して得をするから「節税」になると考えがちですが、ふるさと納税はそもそも寄附であり、減税や節税とは関係ありません。
税負担が少なくなるのではなく、寄附という形で税金を前払いで納め、翌年にその分、税金として支払うお金が安くなっているということ。
つまり、税金を前払いしているイメージが近いかもしれません。
「ふるさと納税」のデメリット③ 限度額を超えると自己負担になる
「ふるさと納税」をした額から2000円を引いた額が戻ってきますが、上限があります。
控除額の上限を超えてしまうと、控除の対象外(全額自己負担)となるので注意が必要!
ふるさと納税のメリットを受けられる上限が個人によって違います。
他の控除との兼ね合いから上限額は、年収や扶養家族、住宅ローンの有無などによって変わってきます。
「自分の場合の上限はいくらか」を知りたい方は、ポータルサイトで簡単に調べられます。
まとめ
税金の前払いもしつつ、お得に返礼品ももらえる「ふるさと納税」のメリット・デメリットをご紹介しました。
気を付ける点はありますが、かなりお得な制度だと思います。
特に最近では、日用品を返礼品でもらう利用者の方も多いようで、家計の節約にもなります。
家計の節約でできたお金を投資などに回して、お金を増やしていくこともできるかも!。
なお、ふるさと納税の区切りは1月1日から12月31日までです。
是非「ふるさと納税」をご検討ください!
おまけ
このたび、我が家では、子供へのお金の教育について実践した模様を電子書籍(kindle版)にして出版しました!その書籍がこちらです!
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XVHJ5P7/ref=cm_sw_r_tw_dp_7RMX4CK1SNP1KRGC1ZFP
我が家で行った家庭内起業の模様をまとめたものです。お子さんのマネーリテラシーを向上させたい方は必見です。
また、実は、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、以下の部分をポチっとお願いします。筆者の励みになっています!
今回は、以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。





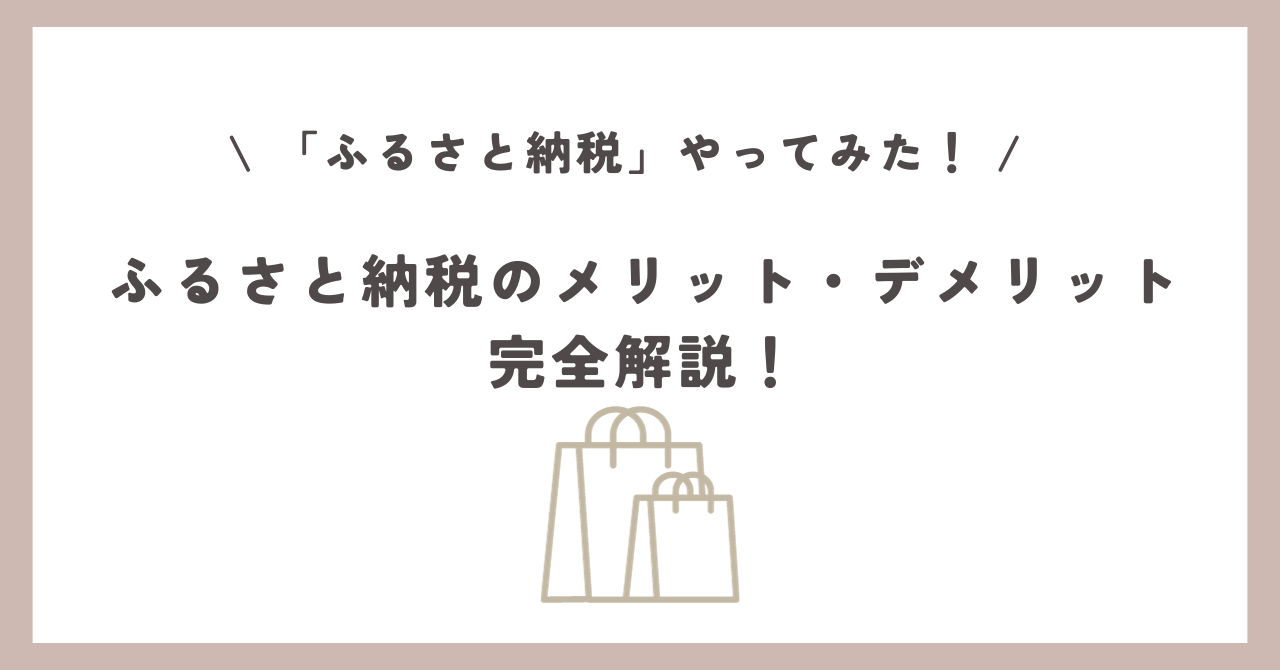






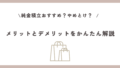
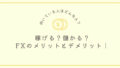
コメント