ご挨拶
どうも。かず~むです。
前回では、株式投資について、ご紹介しました。ご紹介した後に、自分でもいろいろ株式の銘柄を調べていたのですが、少々疲れ気味で、結局何を選んだらいいか分かりませんでした。

そこで、我が家ではまずは、投資信託の商品を購入することから始めることにしました。
この記事を読めば→投資信託とはどういうものかが分かる!かも。
そんな時、ふと証券会社のホームページを見ていると「投資信託」というタブがありました。
金融機関の前に貼ってあるポスターやCMなどで、よく目にする「投資信託」ですが、投資を託すというのは、どういうことなのか!について、興味を持ったので、調べた結果をご紹介したいと思います。
個別の株(銘柄)を選ぶのは大変だった!
例えば、投資を始めようとして、いろいろ会社のいろいろな数字を見ようとしましたが、正直、どこの会社の株を買っていいか分かりません。
しかも、1つの会社の株を買うには、最低の購入単位(単元)が決まっているので、ある程度まとまったお金が必要であることが分かりました。
例えば、トヨタ自動車の株を買うには約100万円必要ですし、ソフトバンクでも約15万円かかります。
さらにまとめていくつか買いたい場合には、もっとたくさんのお金が必要で、10社分買うとしたら100万円単位のお金が必要だということが分かりました。
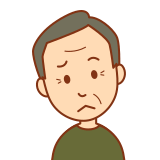
手軽に始められないじゃないか・・・
これは困ります。そんな人のために投資信託という商品があるようです。
投資したいけど自分で大金を使って購入することができなかったり、時間がないしめんどくさい人はたくさんいると思います。
その時に、ファンドと呼ばれる「資産運用のための金融商品やそのような商品を運用する会社」のところにお金を預けて、そのファンドがいろんな会社のをまとめて買ってくれる仕組みがあります。
投資したいと思っている人は、たくさんいるはずなので、皆から少しずつお金を集めてファンドにお金を集めます。
そうすると、自分が、100万円持っていても、1社の株式かしか買えないけど、ファンドが100万円を100人から集めたら1億円が集まることになります。

そして、その資金をファンドマネージャーと呼ばれる投資のプロが、運用してくれます(どこの会社の株をどれだけ、いつ買ったらいいかなど)。
投資信託のそれぞれの商品の説明書に、どういった会社の株を買っているかという記載があります。
投資信託はミックスフライ弁当!?
お弁当に例えることができます。
お弁当を作る場合、スーパーで、唐揚げを買って、とんかつを買って、コロッケを買って、エビフライを買って、漬物を買って、ごはんを買ってと自分で用意するとなると材料費や手間もかかります。
プロのお弁当屋さんに任せて、美味しそうな唐揚げやとんかつなどを選んできてもらう。
その代わり、お弁当屋さんに手数料を支払うというなものです。

その結果、1人だと、コロッケくらいしか買えないけど、同じような想いの人がたくさんいれば、みんなでお金を出し合って、何十人前のお弁当が作れることになって、それぞれが1人前を保有することができるようになります。
お弁当の種類はいろいろあって、お魚メインのお弁当であったり、野菜メインのお弁当であったり、辛口のお弁当であったり、塩分控えめのお弁当であったり。。。
自分の好みにあった商品を選ぶことができます。
どんな商品があるの?
では、どんな組み合わせがあるのでしょうか。
実は、組み合わせが無限大で、日本の株だけで構成されたものだけではなく、アメリカやヨーロッパの株を含めているものもあれば、新興国の株を中心に含めているものなど、国際的な商品もあります。
また、株式だけではなく、国債や債券などを含めているものや不動産や金に関するものを含むものなど、ジャンルも多様で、アップルとかマイクロソフトなどのハイテク株のばかりを含めたものもあれば、AI関連の株を集めたものなどもあり、特定の分野に特化したものも多数あります。
かなり多数の投資信託の商品があり、それだけ選択肢があるということです。
投資信託の商品を買うメリットは?
いろんな銘柄の詰め合わせパックなので、分散投資になります。
例えば、1つの株だけ持っていたとすると、その会社が経営不振だったり、最悪の場合つぶれてしまったりした場合には、投じたお金も大幅に減ってしまいます。
唐揚げ定食を買ったのに、唐揚げがイマイチだったような場合ですね。

唐揚げがイマイチでも、コロッケやとんかつが、とてもおいしければ、全体としてまあまあ良かったということになります。
ひとつの会社が芳しくなかったとしても、他の銘柄がまだありますので、直ちに全滅という事態は発生しません。
つまり、リスクを分散できるということになります。
投資信託の購入の仕方
証券口座を作って、そこに入金すれば購入することができます。買い方としては、口数指定(何口買うか)と金額指定(何円分買うか)の方法があります。
金額指定の場合、100円以上で1円単位から購入できるものがたくさんありました。また、ほとんどの商品が自動積立ができます(毎日100円ずつ自動的に購入するような買い方です。)。
また、投資信託は1日1回、基準価額というのが決まるので、リアルタイムの価格の変動というのはありませんので、1日中、パソコンやスマホに張り付いている必要はありません。

投資信託の商品にかかるコストは?
投資をする上では、必ず注意しないといけないのは、コストです。
投資信託は、プロにお任せしているわけですから、コストがかかるのは、当然です。
ただ、このコストが高すぎる場合には、利益を出すのが難しくなるため、避けた方がいいと思います。
投資信託の商品を、買って、持って、売る、それぞれの場面でかかるコストは主に次のようなものです。
購入コスト
投資信託の商品を購入する時に手数料がかかります。手数料の額は、ファンド又は購入商品ごとに異なります。
高いものは1%取られてしまうものもありますし、中には3%というのも見つけました。無料のものもたくさんありました。
購入しただけで手数料がかかるということは、マイナスからのスタートになってしまうので、あまりに高額な手数料がかかるものは、避けた方がいいかもしれません。
保有コスト
投資信託の商品を保有していることにかかる手数料です。
信託報酬と言われます。投資信託はプロにその運用を任せているわけですから、当然報酬が発生するので、それを支払う必要があります。
これは、購入時手数料と違って、保有している間ずっと支払うことになります。しかも利益が出ている時だけではなく、損失が出ている時にもかかります。
この手数料はどういうものを投資信託の中身に含めるかということと関係しているようですが、あまり高すぎるものはお勧めできません。
売却コスト
投資信託の商品を売る時にかかりコストです。
信託財産留保額といって、売却する際に、解約代金に所定の率を掛けた金額がかかる場合があります。ネット証券なら大した手数料はかからないことが多いようです。

投資の明暗を分けるのは、購入コスト、保有コストです。
ここが本当に重要なようで、全然利益が出ないごみのような投資信託の商品の購入や維持に多額の手数料を支払うことになって、裁判になるようなケースもあるようです。
コストはしっかり吟味して、いわゆるぼったくり商品を買わされないようにしておく必要があります。
投資信託を購入した後のメンタルや時間は?
私は、コロナの時の給付金で投資信託の商品を購入しましたが、リアルタイムの価格というのがなく、値動きは、翌日にならないと分からないので、精神的にも落ち着いています。
「株価が気になって仕事が手につかない!」「トイレに行っている振りをして株価チェック!」などのようなことは、一切なく、株価に一喜一憂することは、今のところありません。
時間的にも過度に投資に時間をかけることなく趣味程度のものとなっています。
まとめ
今回は、投資信託についてご紹介しましたが、投資の目的はひとそれぞれなので、短期的に利益を出したいひとや、ハイリスクハイリターンを求める人はもっと適切な投資手段があるかもしれません。
我が家のような子育てサラリーマン家庭では、将来の子供たちの教育費や何かやりたいことができた時の補助になればとある程度、中長期的な目的で始めることにしました。

それに、物理的にも株価をリアルタイムで見ることも難しいですし、リスクをできるだけ分散させながら着実にお金を増やすことが、今の我が家には合っているかなと思い、投資信託の商品を購入しました。
今回は、以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。







コメント