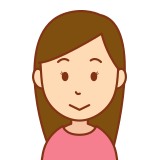
いろんなものが値上がりして家計が苦しい!
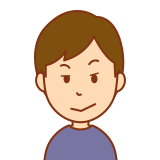
家計管理したいけど、難しいこととか面倒くさいのはイヤ!
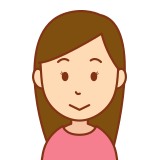
お金が貯まる家計ってどんなことをしているの?
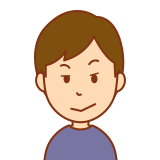
どこまで細かく家計簿をつけないといけないの?
こんな思いや疑問を持った方も多いのではないでしょうか。
最近は物価高。
収入は増えないのに、支出は増えるばかり。
そんな時に大事なのは、家計管理です。
でも、家計管理って、どこまで細かくやればいいか、分からないし、めんどくさい・・・。
我が家でも、こんな思いから、なかなかお金が貯まらず、給料日が待ち遠しい!といったことが一度や二度ではありませんでした。

しかし、そんなズボラな我が家にも最適な家計管理方法がありました!
これを知ってからズボラな我が家でも、しっかり家計管理ができるようになり、安定した生活を手にすることができました。
また、継続することで家計に余裕が生まれ投資用のお金を捻出することもできました。
そこで、この記事では、FPや簿記の資格を持つ筆者が、自身の体験をもとに「どうしたら『できるだけ簡単に』お金を貯めやすい家計管理ができるのか」についてご紹介します。
結論→予算を立てる!
結論、お金を貯めやすい家計管理をするためには「予算を立てる」こと。
理由は、シンプル。
人間は、収入が高くなれば高くなるほど、自然とお金を使ってしまう習性があるから。
我が家でも、以前は、臨時収入があった時には、嬉しくなって、すぐ外食したり買い物したり・・・。
家計は、クローゼットの整理などと同じようなものです。

整理することで、「ああこんなところに着ない服があったんだ」とか、「こんなところに無駄なスペースがあったんだ」ということが分かります。
そこで、どれくらいの収入があって、どれくらいの支出が見込まれるのかを、まず知ることがスタート地点です。
予算を立てて、家計を整理することが大切です。
では、どうやって予算を立てればいいのでしょうか?
どうやって予算を立てるの?
まず、家計の中身を、「収入」と「支出」に分類されます。
さらに、支出は、毎月大体同じ金額になる「固定費」と月によって額が変動する「変動費」に分けます。
そして、「収入」「支出(固定費)」「支出(変動費)の3項目について、予算を立てます。
その際のポイントは以下のとおり。
収入を「悲観的」に見積もる
お金を貯める原資となるのは「収入ー支出」の部分です。
まずは、収入を予測することが大事。
サラリーマンの場合には、所得税から住民税とか健康保険料とか年金とか、通常天引きさた後の金額で予算を立てます。
ここでのポイントは、「できるだけ悲観的になること(マイナス思考になること)」

例えば、残業代は含めない、ボーナスも半分くらいで見積もるなど、臨時収入的なものは、そもそもないものとして見積もるなど。
また、結婚していて共働きの場合だったら、一方の収入は含めないなど、かなり少なめに見積もりることをおすすめします。
その理由は2つです。
- 収入を高く見積もることでそれにつられて支出も高くなるから
- 予期せぬイベントを想定内とするため
実際に我が家でもコロナ禍で収入が減少してしまったり、パートのシフトの関係で収入が減少してしまうことがありました。
しかし、そもそもある程度の減少を見込んで収入を見積もっていたため、そこまでのダメージは受けませんでした。
実際の収入の8割くらいで見積もるのがいいでしょう。
固定費を「正確に」見積もる
次は、支出(固定費)についてです。
「固定費」には、住居費とか駐車場代とか水道光熱費とか保険料とか通信費とか、毎月必ずかかるものを含めます。
固定費は、大体、一定額ですので、見積もるのが非常に簡単です。

なので、固定費はできるだけ正確に見積もるようにしましょう。
そして、ここでは、「貯金したい金額」も含め、実際に設定をします。
例えば、5万円を貯金に回したいのであれば、毎月の給料日に5万円を自動振り込み設定で貯引き出さない口座に移しておくとか、毎月自動的にクレジットカード払いで投資商品を購入する設定するなど。
こうしておくことで、強制的に貯蓄や投資にお金を回す環境が出来上がります。
また、実は、この固定費の見直しは家計改善に効果が抜群です。
1回見直せば、ずーっと効果が続くんで非常に効果が高い。
ちなみに、我が家でも、固定費のうち、通信費と保険料を見直し家計が改善されました。


変動費を「気楽に」見積もる
最後は、「気楽な感じで変動費」を見積もります。
変動費には、「食費」「日用品」「医療費」「交際費」「衣料費」など毎月変動する支出を含めます。
変動費は月によって変動するので、コントロールは難しいし、コントロールすることは、精神衛生上良くありません。
例えば、以前、我が家では、変動費までもコントロールしようとして、食事や買い物をするたびに、「今日の外食は●円まで抑えないといけない」「服は●円まで」ということを考えていました。
結果、なかなか楽しめず、ストレスも溜まる状態に。
そこで、そもそも「変動」するものなので、ざっくり気楽に見積もるようにしました。

いくら変動するといっても、あまりに緩い見積もりをしてしまうと家計管理ができません。
そこで、以下の手順で見積もります。
平均的な支出を知る
具体的には、まずは、平均的な支出レベルを把握します。
例えば、コロナ前のデータになりますが、2019年10月の総務省の家計調査報告によると、変動費については、夫婦2人世帯の場合、おおよそ以下のようになっているようです。(1人世帯なら半分)
- 食費 7万7000円
- 日用品 9500円
- 衣料品 1万円
- 交通通信 4万円(自動車関係費含む)
- 教養娯楽 2万7000円
平均的な資産額を知る
次に、金融庁が行った調査によると金融資産保有額は、だいたい419万円くらいだそうです。
つまり、上記のような支出をする平均的な暮らしをしていたら、このぐらいの資産しか貯めることができません。
もし、平均よりも資産額を増やしたいのなら、平均的な支出よりも全体として変動費を抑える必要がでてきます。
変動費のメリハリをつける
そこで、変動費は気楽に見積もりつつ、お金をかける部分とかけない部分のメリハリをつけます。
変動費のどこを削ると、どれぐらいストレスになるかは、人によって違います。
例えば、食費を削って自炊しても全然ストレスがたまらない人と食事だけにはお金を使いたいという人もいます。
車にはこだわりたいと人もいるかもしれないし、単に移動手段だと割り切れる人もいます。
我が家では、特に旅行や食事にはお金をかけて、衣料品などはあまりお金をかけていません。
大切なのは、自分の価値判断でメリハリをつけて、なるべく満足感を減らさないことです。
予備費を確保する
そして、もう1つのポイントは、予備費の確保です。

変動費というのは月によって振れ幅があるので、予算をオーバーしても大丈夫なように予備の予算を立てておくことも重要です。
例えば、我が家の場合、冠婚葬祭が6月に固まったことがあり15万円くらいが一挙に出て行った月がありました(→ジューンブライドを考えた人を恨みましたw)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
予算を全く立てずに資産を増やしている人はいません。
「予算なくして資産なし!」
そして、我が家でも今回ご紹介した方法で、少しづつですが、家計が改善されてきました。
面倒くさいな~と思っている方も1回やれば、そのまましばらくは放置してもOKです。
一度、がっつり家計に向かいあってみましょう!
おまけ
このたび、我が家では、子供へのお金の教育について実践した模様を電子書籍(kindle版)にして出版しました!その書籍がこちらです!
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XVHJ5P7/ref=cm_sw_r_tw_dp_7RMX4CK1SNP1KRGC1ZFP
我が家で行った家庭内起業の模様をまとめたものです。お子さんのマネーリテラシーを向上させたい方は必見です。
また、実は、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、以下の部分をポチっとお願いします。筆者の励みになっています!
今回は、以上です。最後までお読みいただきありがとうございます。





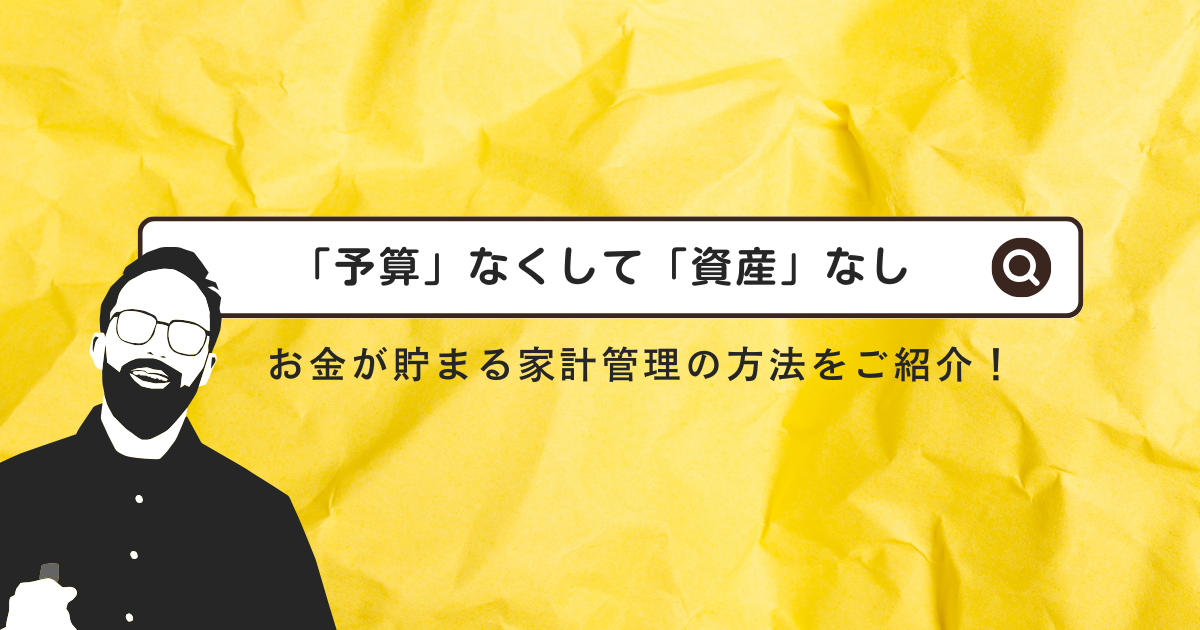

コメント