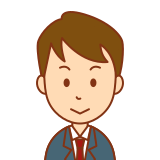
「お金」って大切なのにどうして学校で教えてくれないの?
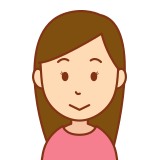
子どもにお金の知識を身につけてもらうには、どうしたらしい?
こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
社会に出て必要になる文字の読み書きや計算は、学校で、かなりの時間をかけて教えてくれます。
お金も、人の一生には欠かせない大切なもののうちの1つです。

しかし、学校では「お金」について学ぶ機会はありません。
筆者は、比較的真面目な学生(自称)でしたが、学校で「お金」のことを教わることもなく、社会人になり、お金の問題に直面した過去があります。
こんなに必要になるのなら、もっと「お金」のことを教えといてよ!
そんな気持ちでした。
今では、簿記やFPの資格を取得し、資産形成も進めることができるようになり、3人の子供たちにも日常的に金融教育をしています。
こうした過程で、湧いた疑問とその答えについてご紹介します。
-
なぜ「お金」のことを詳しく教えてくれないのか?
-
どうやって「お金」のことを学べばいいのか?
この記事を読めば、お金がなぜ学校で教えてくれないのかが分かり、社会に出て困らないようにするためにはどうしたらいいのか、が分かります。
特にお子さんのいるご家庭には必見の内容です。
では、ご紹介します。
「お金」の好感度は悪い!でも、実は、みんな興味津々!
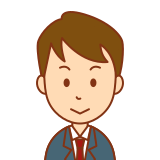
人前でお金のことを話するなんて、はしたない!
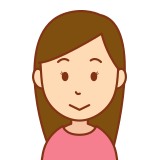
夢さえもっていれば、お金なんて要らないよ!
そんなことを聞いたとことはないでしょうか。
汚いとか下品とか人前で話してはいけないだとか・・・とにかく好感度が悪すぎです!
しかし、一方で。
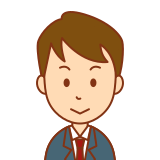
あの会社は、●●円も稼いでいるらしいぞ!
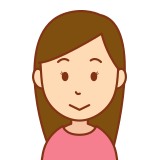
△△さんの年収は、〇〇もあるらしいよ!
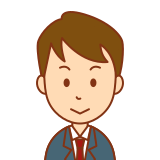
この投資商品を買えば、1年後には資産額が倍になるって!
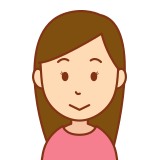
少しでも割安なスーパーを見つけないとね!
と、好感度が低いわりに、みんなお金のこと、特に他人のお金事情については興味津々です!
「お金」の好感度が低いのは、江戸幕府が原因!?
では、みんなが興味津々な「お金」の好感度が低いのは、なぜでしょうか?
これには、諸説あるようですが、ズバリ江戸幕府が原因です!
時の政権は、すさまじい管理能力を備えた徳川家康率いる江戸幕府。
幕府は、とても「人を管理する」のが上手。
「民を生かさず殺さず」
その時代は、「士農工商」という身分制度があったようです。

「士」は武士。
「農」は農民。
「工」は工人(鍛冶屋さんとか)。
そして、「商」は商人。
つまり、江戸幕府は、「お金」を扱う商人をこの身分制度で一番下に位置づけました。
ポイントは、なぜ商人が身分制度の最下位なのか?

一説によると、民に「お金」の知識を持たれ、「お金」をたくさん持たれてしまうと、それを基に武器などを買われてしまう可能性があるから。
民が力を持ってしまって、幕府のコントロールが効かなくなる。そうなると、また、戦国時代に戻ってしまいます。
つまり、「民衆にできるだけ「お金」を持ってほしくない」というのが幕府の本音です。
だから、そんな状態になったら困るから、「民衆には、お金は賤しいものだ!」と思わせて遠ざけておこうと考えたわけです。
どうやらこのころから、「お金」の好感度が悪くなってきたと言われています。
なぜ、今も続いているの?
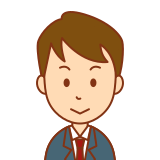
もう江戸時代はとっくに終わってるよ!
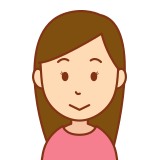
さすがに「令和」の時代にそんな発想はないでしょ!
たしかに、もう江戸幕府はとっくに滅んでいますし、諸外国の文化も根付いています。
しかし、未だに国はいまでも「お金」の教育をしようとしていません。
それは、なぜでしょう。
その答えは、実は、江戸幕府の考え方は残っているからです。

実は、国にとって1番都合がいいのは、「何も考えずに納税してくれる金融知識のない国民」
国を運営しようと思ったらたくさんの「お金」が必要となるので仕方はありません。
「お金」の原資は税金です。税金をできるだけ簡単に徴収するためには相手が無知だとやりやすい。
また、銀行に預けたお金を使って、銀行は国に貸して、国が使っているという構造もあります。
国が「お金」を必要とするときには銀行に「お金」がないといけません。
ということは、何も考えずに妄信的に銀行にお金を預けるっていう国民が一定数いないと国にとって困ることになります。
と、いうことは、子供たちには、お金の知識を持たないまま大人になってもらったほうが、国にとっては都合がいいのです。
これが、学校で「お金」のことを教えない原因だと言われています。
どうしたらいいの?
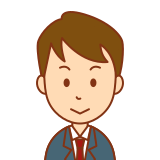
学校で教えてくれないのなら、どうしたらいいの!
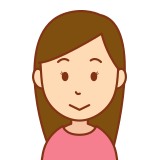
大人だってお金の教育を受けてないのに、どうやって子供に教えるの!
たしかに、このままだと学校は「お金」の教育をしませんし、「お金の教育をしてよ」と言っても応じてくれることは難しいでしょう。
つまり、一人一人が「お金」に関する情報を自分から取りに行かないとダメだということになります。
これからは、自分でお金の情報を取って学んでいくか(子供と勉強していくか)、学校に任せてお金音痴の子供に育てるかで、かなり貧富の差が出てしまいます。
少なくとも、お金にまつわる5つの力「稼ぐ」「貯める」「増やす」「守る」「使う」についての知識やスキルは身に着けておくべきです。
そのためには、大人も子供に学ぶべきだと思います。筆者は、ひとまずこの一冊を読んで子供たちとシェアしてみました。
そのおかげで、子供たちは、メルカリで不用品を販売したり、株式投資をしたりをしながらお金の勉強を続けています。
まとめ
学校が、積極的に「お金」の教育をしないのは、お金に無知な大人を大量生産したいから。
だから、お金のことは詳しくは、今後も学校では教えてないでしょう。
だからこそ、各ご家庭でお金の勉強をしていく必要があります!
自分自身も学びつつ、お子さんとシェアしていけば、一石二鳥です!
是非そんな時には、このブログの他の記事も参考にしていただけると嬉しいです。
きっとお子さんたちの夢を叶える上で役立ちますよ!
おまけ
このたび、我が家では、子供へのお金の教育について実践した模様を電子書籍(kindle版)にして出版しました!その書籍がこちらです!
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XVHJ5P7/ref=cm_sw_r_tw_dp_7RMX4CK1SNP1KRGC1ZFP
我が家で行った家庭内起業の模様をまとめたものです。お子さんのマネーリテラシーを向上させたい方は必見です。
また、実は、ランキングに挑戦中です。今回の記事に共感していただけましたら、以下の部分をポチっとお願いします。筆者の励みになっています!





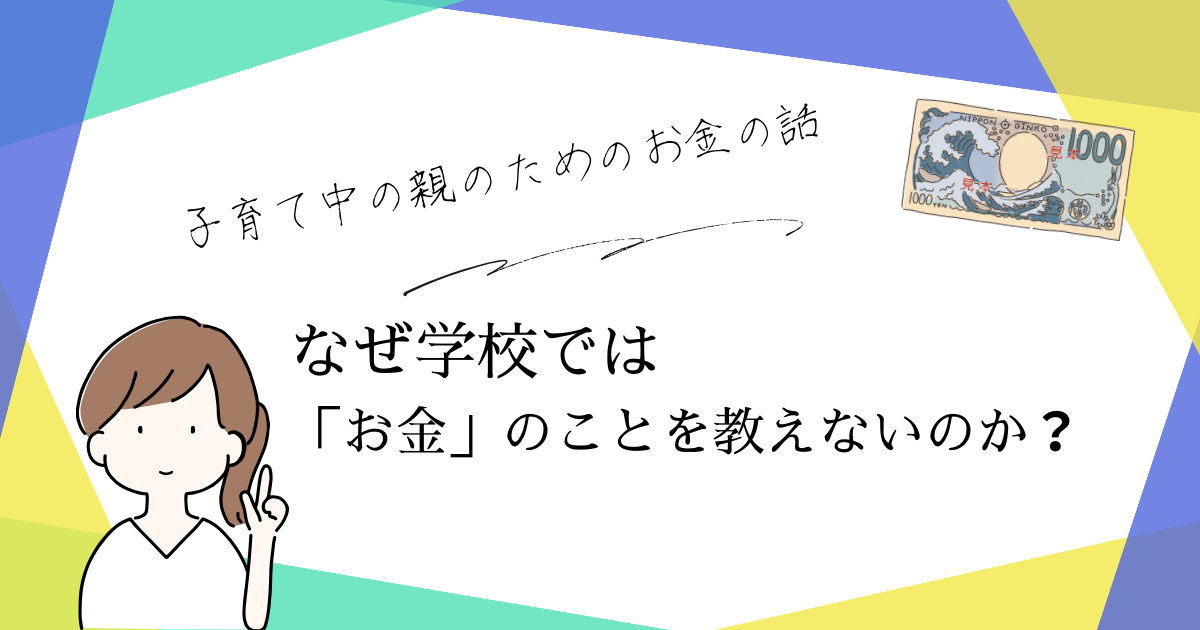
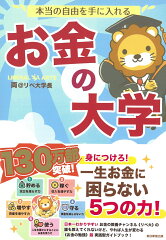


コメント